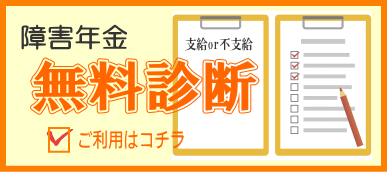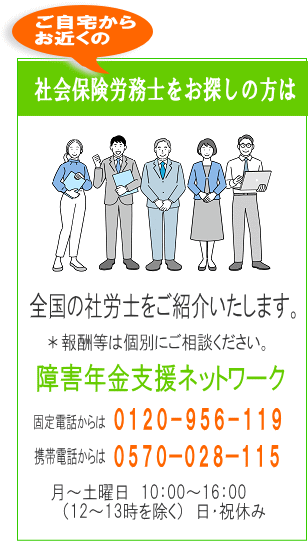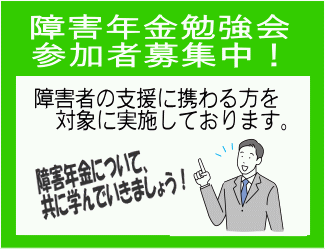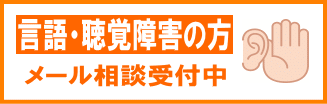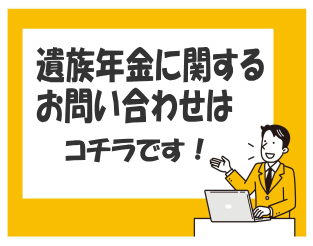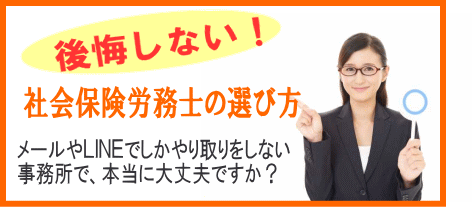受給例
- 網膜色素変性症
- 6年ほど前の健康診断で視力の低下を指摘され、夜盲症状などの自覚もあったことから受診しました。眼の負担がありながらも仕事を続けていましたが症状は徐々に悪化していき、視野の低下で退職に至ったことからご相談いただきました。
数度にわたる面談の後、初診日を特定、納付記録、受診歴を確認させていただき、書類の取得や作成、提出まで全般的にサポートいたしました。結果、障害厚生年金2級の受給が決定しました。
- 視野障害 2つの検査による等級の相違
例えば、脳梗塞による視野障害で障害年金を請求したところ障害手当金の支給決定を受けたとします。もちろん、障害厚生年金3級相当が狙いであれば審査請求を行います。
一方、ゴールドマン視野計による測定では手当金でやむなしの場合でも、自動視野計による測定で診断書を作成した場合、あきらかに3級相当の内容となる場合があります。
自動視野計による診断書を添付し再請求するか、もちろん審査請求で自動視野計による診断書を添付し3級相当を主張する方法もあります。
審査請求が認められた場合、手当金相当と決定されたところまで遡り3級相当とされますので当然受給額は再請求時よりも多いです。
以上のことから、視野障害の場合はゴールドマン視野計と自動視野計の両方の診断書を入手する必要があります。
ただし、認定基準には、「視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定結果を混在させて認定することはできない。」とあります。
末尾にある「混在させて認定することできない」とは、「ゴールドマンの周辺視野角度と自動視野計の中心視野視認点数」で認定するといった「良いとこ取り」はできないという意味です。
よって、双方の測定結果のどちらが上位等級に該当するのか慎重に見極め、場合によっては両方提出することも検討しなければなりません。
要は、診断書に両方の検査結果を全て記載して、周辺視野と中心視野のどちらも同じ検査方法であれば認定されます。(「診断書にはどちらかに記入」とかいていますが)
| NPO会員より、同名半盲で障害手当金から2級になった事例報告がありましたのでご紹介いたします。 ゴールドマン視野計で診断書を作成して認定日請求を行い、1/2以上視野欠損の症状固定で障害手当金を支給された方が、令和7年に自動視野計で検査して事後重症請求を行い障害年金2級に認定されたとのことです。 これまで、ゴールドマンなら1/2以上視野欠損で障害手当金相当となるものが、改正後自動視野計なら周辺視野60点、中心視野34点で2級になる場合があるようです。 思い当たる節のある方は、自動視野計で検査して、もう一度障害年金請求をしてみてもいいかもしれません。 |
|---|