日本年金機構の情報誌『かけはし』で連載されている「障害年金講座」をピックアップしました。 「障害年金とはどんな制度?」「自分は対象になるの?」といった疑問に対し、公的機関ならではの視点で分かりやすく解説されています。制度の基礎から受給のポイントまで、専門用語を噛み砕いて説明されているため、まずは全体像を知りたいという方におすすめの内容です。
□障害認定日(認定簿の特例について) 第94号(令和7年5月1日)
TEL.072-973-7388
〒582-0005 大阪府法善寺4-4-6
日本年金機構の情報誌『かけはし』で連載されている「障害年金講座」をピックアップしました。 「障害年金とはどんな制度?」「自分は対象になるの?」といった疑問に対し、公的機関ならではの視点で分かりやすく解説されています。制度の基礎から受給のポイントまで、専門用語を噛み砕いて説明されているため、まずは全体像を知りたいという方におすすめの内容です。
□障害認定日(認定簿の特例について) 第94号(令和7年5月1日)
線維筋痛症は身体の広範な部位に疼痛をきたす原因不明の慢性疾患です。
主症状は慢性疼痛で、疼痛部位は右・左半身、上・下肢、体軸部など全身の広範囲に及びます。疲労感や全身倦怠感、睡眠障害、不安感、抑うつ感など精神神経症状が認められ、過敏性腸症候群に類似した腹部症状・便通異常、動悸、めまい感、焦燥感や集中力低下、体のほてり感や冷感、微熱などもきたすこともあります。

| QOL | 疼痛部位 | 圧通の程度 | ||
|---|---|---|---|---|
| ステージⅠ | ACR分類基準の 18 カ所の圧痛点のうち 11 カ所以上で痛みがあるが、日常生活に重大な影響を及ぼさない。 | 痛みはあるが普通の生活ができる | 体幹部 | 圧通 (4kg/㎠) |
| ステージⅡ | 広範囲な筋緊張が続き腱付着部炎を併発する一方、不眠、不安感、うつ状態が続く。通常の日常生活がやや困難。 | 痛みはあるが普通の生活ができる | 体幹部 | 圧通(4kg/㎠) |
| ステージⅢ | 痛みが持続し,爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが増強する自力での生活は困難。 | 痛みのため普通の生活が困難 | 体幹部から抹消部痛 | 軽度の圧通 |
| ステージⅣ | 痛みのため自力では体が動かせず、ほとんど寝たきり状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。 | 寝たきりであるが眠れない | 全身痛 | 触痛・自発痛 |
| ステージⅤ | 激しい全身の痛みと共に、膀胱や直腸の障害、口の渇き、眼の乾燥、膀胱症状など全身に症状が出る。通常の日常生活は不可能。 | 寝たきりであるが眠れない | 全身痛 | 触痛・自発痛 |
出典 日本線維筋痛症学会「線維筋痛症診療ガイドライン」
次の表は、上記認定事例の一部をまとめたものです。
| 認定等級 | 重症度分類 | 日常生活動作 | 筋力 |
|---|---|---|---|
| 1級9号 | ステージⅤ | △×と× | 半減・著減 |
| 2級15号 | ステージⅢ | ○△と△× | 半減 |
| 3級12号 | ステージⅡ | ○、○△、△×、片足で立つのみ× | やや減・半減 |
出典 安部敬太編著「詳解 障害年金相談ハンドブック」第2版 515項より一部抜粋
線維筋痛症については、他の傷病に比べ初診日の特定が非常に難しいです。
他の疾病と区別できるような特徴的な症状がそもそも少なく、確定診断が遅れてしまう傾向があり。線維筋痛症の診断を受けるまでに、いくつもの病院を転々とするケースも少なくありません。
初診日については、日本年金機構が線維筋痛症の初診日について公表している「線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて」が参考となります。
上記文書には、確定診断を受けた日だけでなく、条件を満たせば請求者本人が申し立てた日を初診日として認める場合もあるといった内容となっています。
線維筋痛症で障害年金を請求する際は、上記診断書記載事例にもあるように肢体の障害の診断書を使用します。診断書⑨欄に必ず線維筋痛症のステージを記入してもらう必要があります。
なお、精神神経症状がある場合は精神の診断書を使用する場合もあります。精神科医以外に記載を依頼する場合は、そもそもその病院(たとえば皮膚科等)で作成した精神の診断書で認められた前例があるのかを確認する必要があります。
また、最初に線維筋痛症と診断された日を初診として受診状況等証明書を取得し、診断書はうつ病で提出した場合、別疾病と判断されることがあります。
線維筋痛症での請求については、事例ごとに対応が大きく異なってきますので、時間をかけて年金事務所とよく相談をした上で必要書類を揃えていく必要があります。

「障害年金」老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。
障害年金を受給することは、老齢年金や遺族年金をもらうことと同様に、国民として当然の権利です。
ただし、老齢年金と比べると認定基準などが複雑かつあいまいで、初回の請求でつまずくと再請求等のハードルが上がり、受給が難しくなる場合もあります。
①原則として20歳から64歳までの人が受給できる(当然ながら例外もあります)
②年金保険料を一定期間納付している方が対象です(20歳前傷病は別です)
③日常生活や就労に支障がある方が対象です
障害年金 受給額はいくら コチラ>>
障害年金は初診日(現在の障害の原因となる病気やケガで初めて病院にかかった日)に加入している年金制度によって種類が異なり全部で3種類あります。
①障害基礎年金
障害基礎年金は初診日に国民年金に加入している方が受け取ることができる年金です。 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は国民年金に強制加入となっており、自営業 者、農業や漁業に従事している方、その配偶者さらに年金は収めていないですが20歳以前 に障害状態になった方なども対象となります。
②障害厚生年金
障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入している方が受け取ることができる年金です。 会社にお勤めの方やその配偶者の方が対象となります。
③障害共済年金
障害共済年金は初診日に共済組合に加入している方が受け取ることのできる年金です。
共済組合に加入するのは公務員や私立学校の教員の方々です。
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。
なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により5年分が限度です。
事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった場合、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
障害等級 1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
障害等級 2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
障害等級 3級(厚生年金保険のみ)
労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
受給要件について コチラ>>
障害年金請求で必要な書類 コチラ>>

障害の程度が重度の場合、特別障害者手当の申請も可能です。
*身体障害者手帳1、2級程度、または療育手帳A程度の障害が重複している状態、もしくはこれらと同等の疾病・精神障害がある状態が目安といえます。
障害者手帳を持っていなくても申請が可能です。
*納付要件、初診日要件等問われませんので、障害年金請求ができない方でも申請できます。また、65歳以上の方も対象となっています。
身体又は精神に重度の障害があり、日常生活において常に介護が必要な20歳以上の方に対して支給される手当です。基準に当てはまる場合に支給されます。
お住まいの市区町村の福祉担当窓口で申請し、医師の診断書など申請書類にもとづき自治体が認定します。
受給に当たっては、以下の条件を満たす必要があります。
・障害者支援施設などに入所していない
・医療機関に継続して3ヶ月以上入院していない
○支給額
支給額は月額29,590円(2025年度の額)です。
○支給月
原則として、毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。
○所得制限
申請者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以上の場合には、手当を受けることができません。
※扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。

障害年金の請求をしようとして年金事務所に行ったところ、「保険料納付要件を満たさない」言われ途方に暮れる方が結構おられます。
<保険料納付要件>
初診日の前日において、次の①と②どちらかの要件を満たす必要があります。
①初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
②初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること
*初診日が1991年(平成3年)5月1日前にある傷病により障害年金請求を行う場合、「月の前々月」とあるのは「月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月の前月」とするとされています。
*部分免除の場合は、免除額を差し引いた額の保険料を納付していなければ「未納」になります。また納付は初診日よりも前にないと納付要件を満たせません。

<納付要件を満たせない場合>
①初診日とした日よりも前の日に受診した日はないか
その傷病で関連して別の医療機関を受診していないか。
▶▶初診日について:初診日の考え方
②社会的治癒に相当する期間があるかどうか
社会的治癒とは、医学的には治癒していない場合に、社会保険上、被保険者が不利益を受けないための考えだされた概念です。
▶▶社会的治癒を主張する場合
③難病の場合は、傷病名の診断があった日が初診日になることがあります。
難病の場合は、正確な病名がつくまで複数のクリニックや病院を受診していることがよくあります。過去の受診日において初診日の特定が難しく、診断名がついた日が初診日とみなされることがあります。
④初めて1級又は2級に該当する場合
前発の障害だけでは2級に該当しなかったが、後発の傷病(基準傷病)も併せると1級又は2級に該当することによる請求です。
(他の請求との違い)
納付要件、加入要件は基準傷病の初診日で見ます。
初めて1級又は2級になった時点で受給権が発生し支給は請求月の翌月からです(遡及しません)。
*65歳の誕生日の前々日までに「初めて2級」「初めて1級」に該当する必要があります。ただし、請求は65歳以降でもかまいません。
⑤精神疾患(発達障害、うつ病等)の場合で知的障害を伴う場合
発達障害であっても、知的障害を伴うものであれば初診日は出生時(0歳)となり納付要件は問われません。但し国民年金での請求となります(3級無し)。グレーゾーンの方は大人になってから軽度の知的障害であることが判明する場合もあります。
知的障害が3級非該当程度の場合は発達障害やうつ病等での初診時の納付要件が問われることになります。
*療育手帳の有無、発育・養育歴、教育歴などを考慮。
上記④⑤の場合は社労士に依頼されることをお勧めいたします。
特に④の「はじめて1,2級」は障害年金を専門に取り扱っている社労士でも手掛けたこ とが少ない方が多いと思います。

どうしても納付要件が満たせない場合
①厚生年金保険の障害者特例
65歳までに「報酬比例部分」の特別支給の老齢厚生年金が受給している方が、下記の要件を満たした場合、あわせて「定額部分」が受給できます。
・厚生年金保険の被保険者でないこと
・障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にあること
*本人の厚生年金加入期間が20年以上ある場合、加給年金対象となる65歳未満の配偶者や 高校卒業までの子について加給年金も支給されます。
<対象者>
男性: 昭和36年4月1日以前に生まれ(令和3年に60歳)
女性: 昭和41年4月1日以前に生まれ(令和3年に55歳)
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
厚生年金保険等に1年以上加入していた
60歳以上
②特別障害給付金(日本年金機構HPより 2025年4月現在の内容です)
<支給の対象となる方>
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求した方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
(※1)国民年金任意加入であった学生とは
次の(1)または(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
(1)大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
(2)また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各 種学校
(※2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。
(1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(2)上記(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除 く)の配偶者
(3)上記(1)の障害年金受給者の配偶者
(4)国会議員の配偶者
(5)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
(※3)障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
<支給額>
障害基礎年金1級相当に該当する方:令和7年度基本月額56,850円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和7年度基本月額45,480円
*特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
*老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、その受給額分を差し引いた額を支給します。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
*経過的福祉手当を受給している方へ
特別障害給付金の支給を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
*特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給します。
支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分を支給します。(初回支払い等、特別な場合は奇数月に前々月までの分の支払いを行う場合もあります。)
<所得による支給制限>
受給者本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。
支給停止となる期間は、10月分から翌年9月分までとなります。
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
*特別障害給付金の審査・認定・支給事務は、日本年金機構が行います。
③特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当が支給されます。
<支給要件>
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
<支給月額>(令和7年4月適用)
29,590円
<支払時期>
特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
<所得制限>
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
障害年金請求をした結果、不支給の場合は、「国民年金・厚生年金保険の支給しない理由のお知らせ(不支給決定通知書)」が届きます。不支給決定通知書と一緒に同封された「決定の理由」と記載された書類に不支給の理由がざっくりと示されていますが、より詳細な理由をしるために障害状態認定調書を入手する必要があります。
もちろん、2級だと確信して請求を行った結果3級と判定されたような場合にでも、どのような理由で決定されたのかその経緯を知るため障害状態認定調書の開示を求めていきます。
①「現症日」
サンプルの場合は認定日請求のため、診断書は障害認定日と請求日の2枚提出となります。障害認定日及び請求日現症の日付です。
②-1「目安」
診断書の「日常生活能力判定」及び「日常生活能力の程度」を数値化し、「精神障害に係る等級判定ガイドライン」の等級の目安を使い「等級目安確認シート」を作成し、該当する障害等級が記入されます。
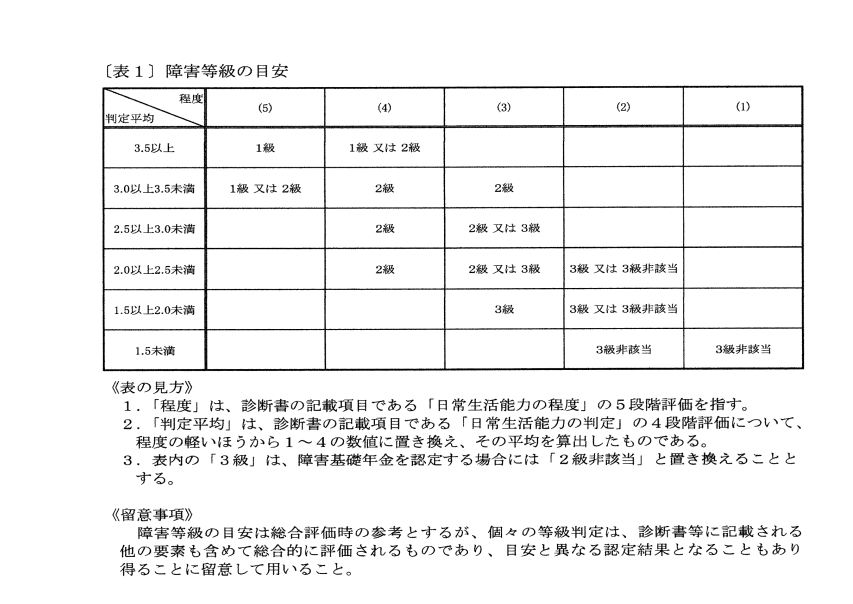
②-2 事前確認
日本年金機構の職員が「事前確認票」を作成します。等級目安確認シート右下の「日常生活能力の程度」で該当する等級を「事前確認票」の左側に記入します。さらに、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容から、「事前確認票」へ等級判定材料となる情報をピックアップし、チェックをしていきます。
抜き出した情報をもとに再度障害等級の判定を行います。目安確認シートでは2級であったものが、右欄「事前確認」では3級に○をされている場合もあります。その際には等級判定において考慮すべき要素及び根拠が記載されます(中央部分)。
*考慮すべき要素については後述
新規裁定については、請求を受けてから職員が納付要件等の確認をした上で事前確認票の作成を行い、認定医(障害認定審査医員)が当該事前確認票も参考に、医学的な観点から障害等級を判断しています。
一方、再認定では、事前確認票の作成はなく、前回の認定も参考に認定医が医学的観点から障害等級を判断しています。
| 認定医について 職員が担当する認定医は1名~3名程度であり、日程上最も早く対応が可能な認定医に依頼しているようです。 令和7年4月29日 共同通信により 障害年金判定に際し、認定医の判断を誘導するような対策文書が存在するのではないかとの報道がありましたが、職員への内部ヒアリングの結果そのような文書の存在は確認できなかったとのことです。(令和7年6月11日 調査報告書) |
|---|

③「S]
セカンド。複数(2名)の認定医により審査されたことを表しています。
④障害の等級
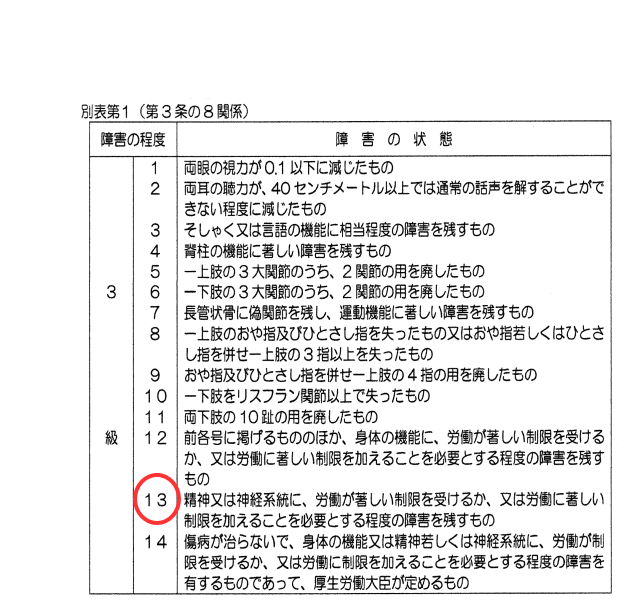
⑤適用する認定基準
障害年金認定基準第8節-2認定要領-A(08A)
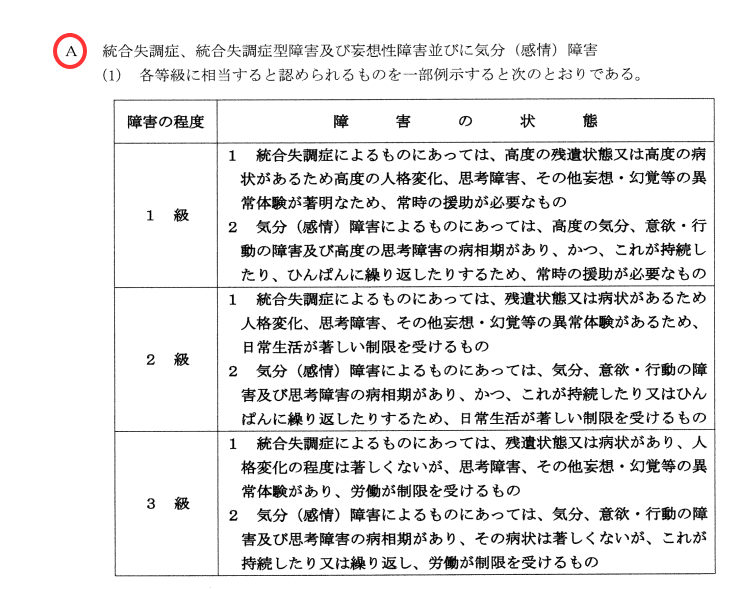
⑥特に考慮した事項の番号
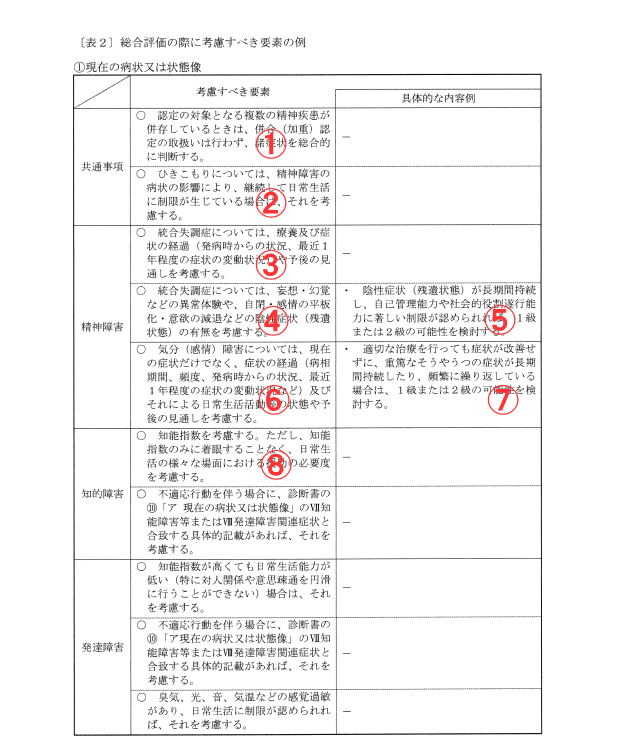
考慮すべき要素-6
「気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。
」
⑦具体的な等級判定理由、不支給・却下とした理由
不支給となった場合、2級該当を3級と判定された場合等の理由が記載されます。
例:⑩イ ⑪ カルテから○○○○あり 等
⑩、⑪は診断書(精神の障害用 様式第120号の4)の記載項目です。
*なお、具体的な等級判定理由について、「⑩ウ」や「カルテ、就労状況により3級」等の記載がよく見受けられます。
開示請求をかけて判定理由を知る上で、このような記載は判断の理由としては極めて不明確であると言えます。「⑩ウ」のどのような点が上位等級を検討する要素で、どのような点が下位等級を検討する要素なのか、明確に記載されている必要があります。
「⑩エ」を理由として、3級非該当とされる場合もありますが、一般就労していることのどの部分が下位等級を検討する要素になっているのか明確な根拠が示されるべきですが、現時点では、これまでの請求事例より推測するしかありません。

①趣旨
審査請求を行う上で求めていくない内容を記入します。
例:「裁定請求日において障害基礎年金2級を認定すること」
「障害認定日及び裁定請求日において障害厚生年金の受給権を認めること」
②理由
開示請求で入手した認定調書等をもとに、処分内容がどのような根拠のもとに下されたかを推測し、それに対する反論を考えていきます。
例えば、2級相当のものが不支給となった場合、
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(3)総合評価-①には「 診断書の記載内容に基づき個別の事案に即して総合的に評価した結果、目安と異なる等級になることもあり得るが、その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判定する。」と定められています。認定調書の⑦等に記載された内容をもとに、不支給と判定した理由に合理的かつ明確な根拠があるのかを考えます。
障害認定基準、精神の障害に係る等級判定ガイドラインそして過去の社会保険審査会での採決例等を元に理論構成していきます。診断書や病歴・就労状況等申立書などに記載された事実を法令、ガイドラインにあてはめ保険者の主張の矛
盾、解釈の間違い、不備を突いていきます。
残念ながら、年金事務所での相談で具体的なアドバイスをもらうことはできません。請求者一人一人で全く事情が異なってくるため一般論では対処しようがないからです。
ご相談者の中には、「診断書の内容が軽く書かれていたので、改めて主治医に診断書を修正をさせた。これを提出すれば受給できるか」とのお問い合わせをいただくことが有ります。
しかしながら、よほどのことがないかぎり診断書の修正、補正は認められないと考えた方がいいでしょう。
原処分を受け審査官の決定書の内容を知った後に、医師が請求人の要請に基づいて作成された診断書等については、当時の診療録等の客観的資料に基づいて作成された診断書とは認められません。患者に泣きつかれて修正、補正したものを後から提出しても認めないということです。

①とりあえず自分で請求をしてダメなら不服申し立てをする。
②支援機関のサポートを受けて、年金事務所とも相談の上で手続きを進める。
③社会保険労務士に依頼する。
①②の場合
・診断書の不備を見極め、理由、根拠を示したうえで医師に修正させることがで きるか。
⇒もちろん、ごり押しでするのではなく、記載要領等をもとに記載時の留意事項 等を説明したうえで修正していただく必要があります。)
・年金事務所での説明、病歴・就労状況等申立書作成時において、情報の取捨選択をしっかりと行えるかどうか。
⇒不必要な情報まで相談、もしくは申立書に記入するとその内容が後々まで尾を引く可能性があります。
・支援機関等でサポートしてもらう際に、不支給となった場合、不服申し立て迄サポートをしてくれるか。
⇒とりあえず年金事務所で言われたとおりに書類を作成して提出をし、不支給となったら「もう無理です」では話になりません。
障害年金を専門に扱っている社会保険労務士であれば、不服申し立ても当然ながら取り扱っています(全員とはいいませんが)。審査請求等を行うことで、保険者が診断書やカルテそして申立書のどのような点を問題としてくるのかおおよそ検討がつきます。
先にも述べましたが、不備な診断書を提出すると、その後不服申立をしても決定が覆ることはありません。後出しジャンケンで請求時に提出した診断書を、審査請求の段階で別のものと差し替え、認められる等ということは非常に稀です。
要は、最初の請求が一番肝心だということです。”ダメなら不服申し立て”という発想は非常にリスクが高いです。
受給権は最初の1回目でしっかりと勝ち取る(語弊はありますが、実際、勝負所は初回請求時です)ことが重要です。
保険者がチェックをするポイントを見極め、医師への診断書作成を依頼し、障害の状態・程度及び日常生活状況等矛盾の無いように申立書を作成していく必要があります。
以上、不服申し立ては請求時の数倍労力と知識が必要となります。請求時の手順についてはネットでいくらでも情報が公開されていますが、審査請求、再審査請求についてはそのような制度があるというレベルで、実際どのようにすべきかという情報はどこを探して見つかりません。
依頼を受けた社会保険労務士は請求者の個々の状況を見極め、数日から数週間かけて審査請求書類を仕上げていきます。個々の事例を取り上げネットに情報を上げたところで、当事者以外には全く意味のない情報、知識となります(考え方は参考になりますが)。また、個人情報の絡みもあり具体的な情報入手は困難です。
*現時点で入手可能かどうかは不明ですが、
下記書籍は事例掲載が豊富で非常に役立ちます。
「障害年金 審査請求・再審査請求」(日本法令)
なお、NPO法人 障害年金支援ネットワークでは全国の社会保険労務士をご紹介しております。
審査請求をする方が良いのか、した場合の受給の可能性、さらに再請求について等、無料相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(社会保険労務士の利用を無理強いされるようなことは一切ありませんのでご安心ください)
↓↓↓大阪、奈良等一部地域を除き出張相談可能です。

本来、障害年金の初診日は「障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日」をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
また、過去の傷病が治癒し、同一の傷病で再度発症(再発)した場合は、「再発し医師等の診療を受けた日」になります。
社会的治癒とは、医学的には治癒していない場合に、社会保険上、被保険者が不利益を受けないための考えだされた概念です。

社会的治癒について法令上の明確な定義はありませんが、いくつかの裁決例で以下のように述べられています。
| 引用:平成26年(厚)第892号 平成27年9月30日裁決 令和3年(厚)台342号 にも同様の引用あり 社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合には、「社会的治癒」を認め、治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許されるものとされており、当審査会もこれを是認している(以下省略) |
|---|
| 引用:令和3年(厚)第755号 社会保険の運用上、 いわゆる社会的治癒の概念の下に、 傷病が医学的な意味では治癒したとはいえないが、 その症状が消滅して社会復帰が可能となり、 かつ、 投薬治療を要せず、 外見上治癒したとみえるような状態が、 ある程度の期間にわたって継続した場合には、 これを治癒に準じて取り扱うことが承認されているところであるが、 当審査会では、 その適応の判断は、 それぞれの疾病の特性や個人の社会的背景に応じて取り扱うことが、 社会的治癒の理念的にふさわしいとしている。 |
|---|
| 引用:令和3年(厚)第1101号 社会保険の運用上、 過去の傷病が治癒した後再び悪化した場合は、 再発として過去の傷病とは別傷病として取り扱い、 治癒が認められない場合は、 過去の傷病と同一傷病が継続しているものとして取り扱われるところ、 医学的にば冶癒に至っていないと認められる場合であっても、 軽快と再度の悪化との間に、 いわゆる「社会的治癒」が あったと認められる場合は、 再発として取り扱われることとなるが、この社会的治癒があったと認め得る状態としては、 相当の期間にわたって症状がなく医療(予防的医療を除く。 )を行う必要がなくなり、通常の勤務に服していたことが認められる場合とされている。いわゆる「社会的治癒」については、 治癒と同様に扱い、 再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許されるものとされ、 当審査会もこれを是認しているところである。 |
|---|
医学的には治癒していなくても、社会生活を問題なく過ごせていた期間が一定以上あることが客観的に認められれば、一旦は治癒したとものとして以前と同じ疾患が再び生じても新たな傷病を発病したものとみなすという考え方です。
基本的に社会的治癒は請求者の利益を守るための概念です。本人が何も主張しなければ、原則どおりの初診日が障害年金の初診日になります。
障害年金請求において以下のような場合、社会的治癒を主張するメリットがあります。

医学的な治療を行わず安定した社会生活を送ることができ、薬等も飲んでいない状態が続いていることを証明。(病気などの経過観察や予防に関するケアを医師の判断のもとで行っている場合は、社会的治癒と認められる可能性があります)。
就労、家事等問題なく行われており、社会生活に支障をきたしていない状態が一定期間(概ね5年以上)続いていたことを証明。また、外見上において自身も他者も、病気などが回復したと見て取れる状態であることが重要です。
*どの程度の期間があれば社会的治癒が認められていたのかについては、過去の裁決例でも確認することができません。年月日は全て伏せられているためです。
社会的治癒とは、傷病が、医学的な意味で治癒したとは言えないが、その症状が消滅して社会復帰が可能となり、かつ、治療投薬を要せず、外見上治癒したと見えるような状態がある程度の期間にわたって継続することであり、保険給付上はこれを治癒に準じて扱うことが承認されている。もっとも、治療投薬については、全くこれをしない状態であることは必ずしも必要ではなく、医事的・経過観察的な治療が継続していても社会的治癒の成立を妨げないとされる。社会的治癒と認めるのに必要な寛解期間の長さは、傷病の性質によっても異なり(たとえば癌の手術をしたような場合や精神病の場合には、ある程度長めな寛解期間が必要とされる傾向にある)、また、障害を事由とする年金給付の場合と健保法上の傷病手当金の場合戸でも、必要とされる寛解期間の長さは同じではない。 加茂紀久男『裁決例による社会保険法』民事法研究会2011,203項 |
|---|
保険者から社会的治癒を持ち出して、請求者の主張する初診日を後ろにずらすようなことは認められないとされています。但し、実際には保険者が社会的治癒を援用していくる場合もあります。
初診日は再発後の初診日を記入。再発後の病院で受診状況等証明書を取得
病歴・就労状況等申立書には初診日(再発前)から現在までの状況を記入
*問題なく社会生活を送れていた旨記載
診断書には寛解して、治療の必要がない期間が続いていたことを記載してもらう
医師の診断書
医師に診断書を書いてもらう際に、過去に病気などの治療をしていけれども、それが寛解し、治療を行わないでもよい期間が続いたことなどを明確に記載してもらう必要があります。
給与明細
就労が一定期間継続しており、意欲的に働いた結果として昇給・賞与の支給があったことを証明。
厚生年金ではなく、国民年金だった場合、自営で仕事していた証明、所得証明、留学・資格取得等の証明などの根拠を出す必要があります。
その他、旅行に行った際の写真、草野球等で楽しくプレーしている写真等を収集し添付して提出することも可能です。

以上、概要を説明いたしましたが、実務的には社会的治癒の証明は困難なケースが多いです。
第三者から見ても寛解し、問題なく社会生活が遅れている状態であること数々の書類を揃え証明できるかがポイントです。
初診証明ができず、ただ単に自己判断で受診を辞め、5年経過したから社会的治癒を主張してみる、で認められる可能性は低いです。
特に就労していない場合、または就労していてもバイト程度であった場合は社会生活が問題なく過ごせているとはされないことが多いです。
社会的治癒は請求者本人を救済するための精度ですが、自力で書類を揃えたり、診断書作成のポイントを医師に説明することは非常に難しいのも事実です。一度障害年金を専門に取り扱っている社会保険労務士に相談してみることをおすすめ致します。


本人死亡後でも障害年金請求の要件を満たす場合、障害認定日請求(未支給年金としての請求)は可能です。
なお、死亡後は認定日請求のみで事後重症請求はできません。
*年金の請求は未支給年金を除いて本人しかできないことから、未支給年金請求という形で 障害年金の請求を行います。
① 初診日に国民年金または厚生年金に加入していること
② 初診日の前日において、前々月までの保険料を全被保険者期間の3分の2以上納付してい ること。
※初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満の場合、初診日の前日において、前々月までの直近1年間に保険料の未納がない。
③ 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)において、障害等級に該当していること。
障害認定日から3ヶ月以内に受診があり、かつ、カルテが残っているか。
請求人死亡から5年以内か(死亡後の請求の時効が5年のため)。
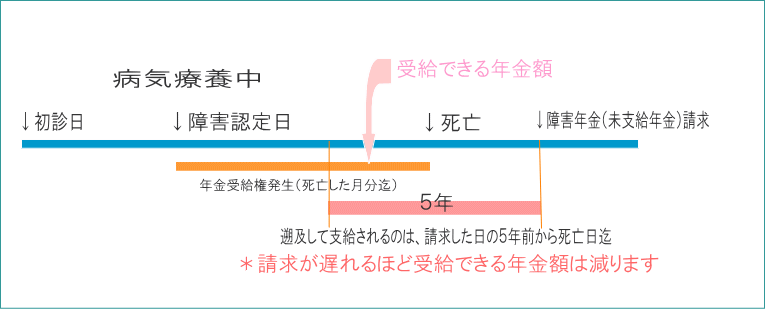
次の場合、請求はできません。
亡くなる直前には障害等級に該当する症状であっても、障害認定日時点では、障害等級に該当するほどの状態ではなかった場合(審査をされるのはあくまでも障害認定日の症状)。
カルテが破棄もしくは認定日から3カ月以内に受診しておらず、障害認定日時点での診断書を作成してもらえない場合。

未支給年金を請求できる人は、亡くなった方と当時(死亡時)に生計を同じくしていた方です。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他 1〜6以外の3親等以内の親族
なお、「生計を同じく」していれば未入籍の内縁の妻でも請求可能です。また、必ずしも同居が条件ではなく、別居中でも亡くなった方から経済的な援助を受けていたり、定期的な連絡や訪問をし合う関係にあった場合には支給対象となります。

保険料納付済み期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合わせた期間が原則25年以上ある人が死亡すれば条件を満たすことができます。厚生年金の被保険者として働いていたことがあり、きちんと年金を納めていれば45歳以上の方は要件を満たすことができます。
原則、死亡した人の報酬比例部分の年金額の4分3に相当する額となります。計算のもとになるのは、実際に厚生年金に加入していた被保険者期間の月数です。入社10年目で死亡した場合、120月が計算の基礎となります。
ところが、障害年金1,2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは短期要件に該当し、原則として死亡した人の被保険者期間の月数が300月未満の時は、計算上は300月あるものとして計算をしてもらえます。
○死亡後に障害年金請求を行う
病気療養中で障害年金の請求を行っていなかった場合でも、死亡後に障害年金の請求を行い受給権(1,2級)を得ることで、遺族厚生年金の支給額を増やせる場合があります。
*厚生年金の被保険者であった人が、被保険者であった間に初診日がある傷病により、その初診日から起算して5年以内に死亡した時は短期要件となります。場合によっては、障害年金の認定日請求が可能です。
○死亡した方が障害厚生年金3級を受給していた場合
障害厚生年金の3級の受給権者が死亡した場合、「死亡の原因となった傷病」と障害厚生年金の対象となっている傷病との間に相当因果関係があると認定されると、死亡時に障害等級1級又は2級に該当する状態であったとされ、短期要件を満たすことがあります。
以上、家族が病気療養中の時は、日々の生活が大変で、なかなか障害年金の請求など考える余裕がないという方も少なくありません。
しかし、そのために障害年金を受給できないばかりでなく、場合によっては遺族厚生年金すらもらえない、もしくは低額の年金だけ、ということになると、残された家族が受ける不利益は決して小さくはありません。
死亡後の障害年金については、年金事務所や役所からのアドバイスを期待することはできず、知らないままスルーされている方が多いのが実情です。
少しでも可能性があるのであれば請求することをお勧めし致します。

障害年金請求の結果不支給決定や納得のいかない等級支給決定をうけた場合には、不服の申立て(審査請求・再審査請求)をすることができます。

不支給の場合は、「不支給決定通知書」が届けられますが、通知書に同封されている「決定の理由」の記載のみでは実際どのような理由で決定に至ったのかその理由がはっきりとしはません。不支給の理由を明らかにしたうえで対策を立てていかないと、不服申立てを行っても同じ結果が出るだけです。
不服の申し立てを行うのであれ、まず保険者がどのような経緯でその決定を下したのかを知る必要があります。そのためにも日本年金機構に個人情報の開示請求を行い、審査の基準、根拠等具体的な内容が記載された内部書類である認定調書を取り寄せる必要があります。認定調書を読み解くことで、不支給決定の場合であれば、不支給に至った理由が明らかになり対策が立てやすくなります。

請求書には収入印紙300円分を貼付けます。
添付書類としては運転免許証や個人番号カードなどの本人確認書類を同封、開示請求を郵送で行う場合にはさらに住民票(開示等請求の前30日以内に交付されたもの)を同封します。
保有個人情報開示請求書<<標準様式第 2-1>を使用します。
1「開示を請求する保有個人情報(具体的に記載してください。)」欄には、「□□(氏名)基礎年金番号〇〇〇〇が令和◯年◯月◯日に受けた障害基礎(厚生)年金の不支給決定に関して、その根拠や審査の経緯がわかる書類一式」と記入します。
送付先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
中央合同庁舎第5号館2階
厚生労働省大臣官房総務課公文書管理・情報公開室
こちらの場合は指定金融機関の口座へ振込により300円納付します。
振込明細書等振込を確認できる資料の写しを開示請求書に添付して提出します。
なお、振込手数料は請求者の負担となります。
添付書類
年金事務所の窓口へ提出する場合
請求者本人の氏名および現住所が記載された、運転免許証や個人番号カードなどを提示・提出します。
本人確認書類の複写物(コピー)に加えて、住民票の写し(ただし、開示等請求の前30日以内に交付されたものに限る。)を添付して送付します。

開示請求のあった保有個人情報の開示・不開示を決定されたのち、開示請求者に書面(郵送)により通知されます。開示・不開示の決定は、原則として開示請求書を受け付けた日から30日以内(開示請求の補正等に要した日数は含まれません。)ですが遅れる場合もあります。
開示決定の通知を受けた後、請求者は通知のあった日から30日以内に、開示決定通知に同封された「開示の実施方法申出書」に希望の開示方法(写しの交付、全部)にチェックを入れ、指定された金額分の切手を同封し提出(郵送または来所)します。
返送後数日で開示書類が郵送されてきます。
*医師照会で提出した診療録も同封されています。
なお、障害年金請求の際に提出した受診状況等証明書や診断書等の写しが手元にない場合、住所地を管轄している年金事務所に電話をして(基礎年金番号を手元に)、提出書類一式のコピーを送って欲しい旨伝えると2~3週間で自宅に送られてきます。
個人情報を入手してからどのような行動をとるかによってその後の人生が大きく変わってくると言えます。
・不支給決定は明らかに失当である場合は審査請求で争う意味があります。
・現状、症状、障害状態が認定基準に該当しない場合、時間をおいて再請求を行う等、今後の対応を検討する必要があります。
・症状は認定基準に該当しているものの提出書類に不備があった場合。
医師の意見書等を添付し審査請求を行うか、それとも再請求をするか。
・再請求を行う場合は、診断書はどれを使うか。
転院をした上で作成を依頼する方がよいかどうか。
・申立書の内容は的確に現在の症状を伝えられていたか。
伝えられていなかった場合、どのようにすれば医師に正確に自分自身の症状を 伝えることができるのか。
同じ間違いを二度しないための細心の注意が必要です。
社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移
*上記の件数は障害年金に関する不服申し立てだけの数字ではありません。
以上、個人情報は入手したもののその後の対応がご自身では難しい場合がほとんどです。
審査請求までの期間は原処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。個人情報を入手した時には、1カ月前後しか残されていない場合が多いです。くよくよと悩んでいる時間はありません。再請求、再々請求になる毎にハードルは上がっていきます。
ご自身での請求に行き詰まりを感じたら、まずは一度障害年金専門の社労士にご相談されることをお勧めいたします。

*前年度から1.9%の引き上げとなります。
*昭和31年4月2日以降生まれの方の金額です。
(1)障害基礎年金でもらえる金額
【1級】 1,039,625円(子供がいる場合は加算)
【2級】 831,700円(+子供がいる場合は加算)
子供の加算
①年齢要件
18歳到達年度の末日(3月31日)までの子供
20歳未満で1級または2級の障害状態にある子供
②扶養要件
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持する子
③加算額
第1子・第2子 各 239,300円
第3子以降 各 79,800円
(2)障害厚生年金でもらえる金額
【1級】 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がいる場合は加算)
【2級】 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がいる場合は加算)
【3級】 報酬比例の年金額
(最低保障額 623,800円)
【障害手当金】 (一時金) 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,247,600円)
(3)配偶者の加算
①配偶者の条件
生計を維持されている65歳未満の配偶者。なお、配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金(被保険者期間が20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受けられる間は、配偶者の加算は止まります。
②加算額
239,300円
(4)年金生活者支援給付金
障害基礎年金の受給権者で、かつ前年の所得が4,721,000円+扶養親族数×38万円以下の方等に支給。
*障害年金等の非課税収入は年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれませ ん。
*所得は扶養家族等の数に応じて増額されます。
給付額 障害基礎年金 1級の方 月額 6,813円
障害基礎年金 2級の方 月額 5,450円
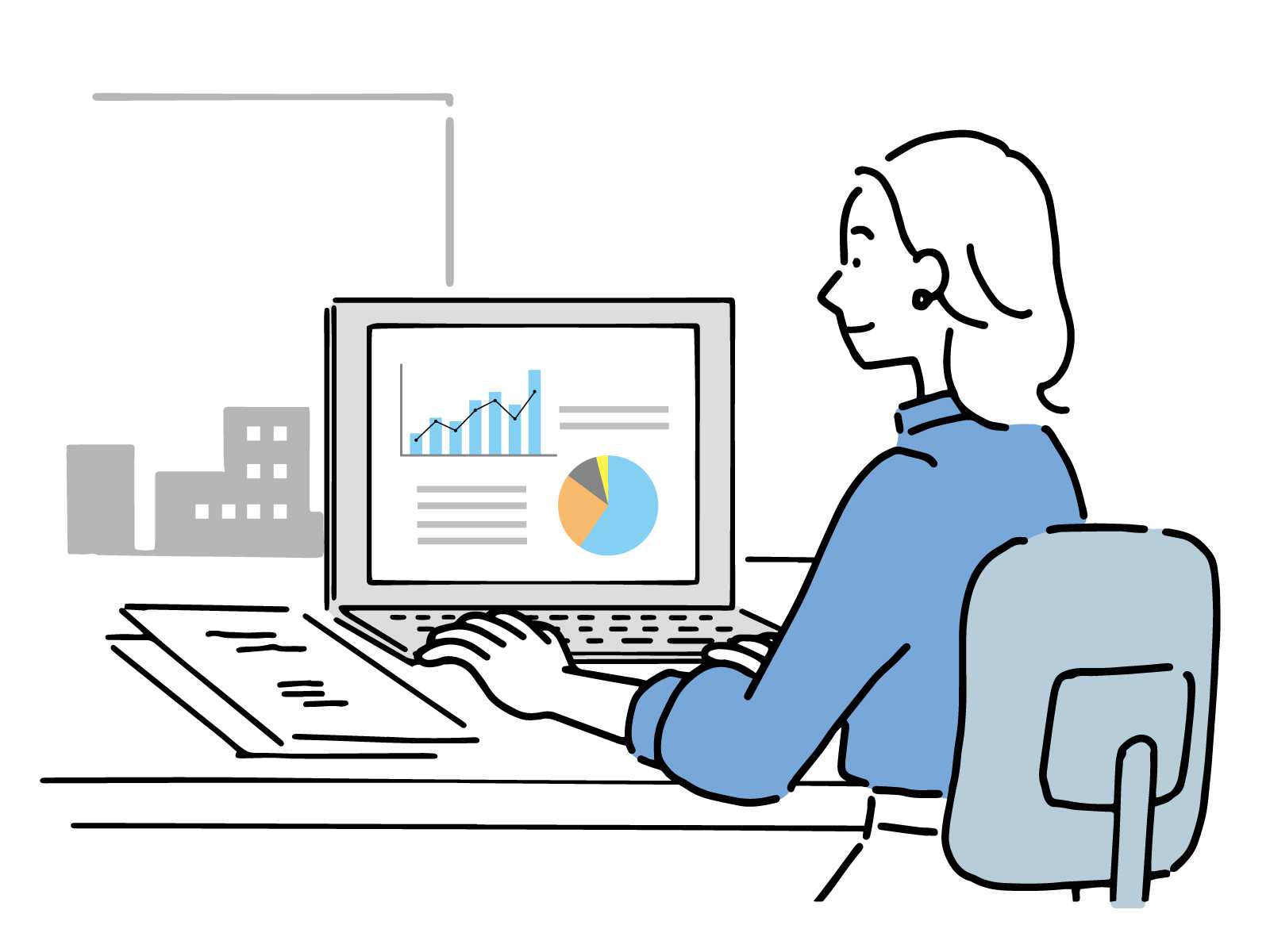
(1)障害基礎年金でもらえる金額
【1級】 1,020,000円(子供がいる場合は加算)
【2級】 816,000円(+子供がいる場合は加算)
子供の加算
①年齢要件
18歳到達年度の末日(3月31日)までの子供
20歳未満で1級または2級の障害状態にある子供
②扶養要件
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持する子
③加算額
第1子・第2子 各 234,800円
第3子以降 各 78,300円
(2)障害厚生年金でもらえる金額
【1級】 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
(+配偶者がいる場合は加算)
【2級】 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がいる場合は加算)
【3級】 報酬比例の年金額 (最低保障額 612,000円)
【障害手当金】 (一時金) 報酬比例の年金額×2年分
(最低保障額 1,224,000円)
配偶者の加算
①配偶者の条件
生計を維持されている65歳未満の配偶者。なお、配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金(被保険者期間が20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受けられる間は、配偶者の加算は止まります。
②加算額 234,800円
③報酬比例の年金額の計算式(簡略)
A:平成 15 年3月以前の平均標準報酬月額× 7.125/1000 × 平成 15 年3月以前の被保 険者期間の月数
B:平成 15 年 4 月以後の平均標準報酬額× 5.481/1000 ×平 成 15 年4月以後の被保険 者期間の月数
●年金額= A + B
※1 被保険者期間の月数は、300 月に満たない場合は、300 月として計算します。
※2 障害認定日の属する月の翌月以後の被保険者期間は年金額の計算に算入されません。
※3 計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額は現在の水準に置き換えて計算します。
〇年金生活者支援給付金
障害基礎年金の受給権者で、かつ前年の所得が4,721,000円+扶養親族数×38万円以下の 方に支給。
*障害年金等の非課税収入は年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。*所得は扶養家族等の数に応じて増額されます。
給付額 障害基礎年金 1級の方 月額 6,638円
障害基礎年金 2級の方 月額 5,310円

(1)障害基礎年金でもらえる金額
【1級】 1,017,125円(子供がいる場合は加算)
【2級】 813,700円(+子供がいる場合は加算)
子供の加算
①年齢要件 18歳到達年度の末日(3月31日)までの子供 20歳未満で1級または2級の障害状態にある子供
②扶養要件 障害基礎年金の受給権者によって生計を維持する子
③加算額 第1子・第2子 各 234,800円
第3子以降 各 78,300円
(2)障害厚生年金でもらえる金額
【1級】 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がいる場合は加算)
【2級】 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がいる場合は加算)
【3級】 報酬比例の年金額 (最低保障額 610,300円)
【障害手当金】 (一時金) 報酬比例の年金額×2年分
(最低保障額 1,220,600円)
配偶者の加算
①配偶者の条件 生計を維持されている65歳未満の配偶者。
なお、配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金(被保険者期間が20年以上ま たは中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受けられる間 は配偶者の加算は止まります。
②加算額 234,800円
日本年金機構HP参照
重度の障害があり、日常生活において常に介護が必要な20歳以上の方に対して支給される手当です。基準に当てはまる場合に支給されます。
精神疾患で障害年金2級相当で、身体障害者手帳3級近くの障害が重複していれば支給される可能性があります。
寝たきり等で長期にわたり安静を必要とする方、立ち上がることがでず、手・腕が動かせない、目がみえにくい・耳が聞こえにくいなどの生活困難な症状を 2 種類以上重複している方で所得制限に該当しそうにない場合は、まずは請求してみるべきです。
初診日、納付要件がありません。納付要件が無く障害年金を受給できない方でも請求ができます。
65歳以降でも請求可能です。
重度の認知症、要介護4・5の認定の高齢者でも受給可能です。
老齢年金(障害年金)等公的年金との併用が可能です。
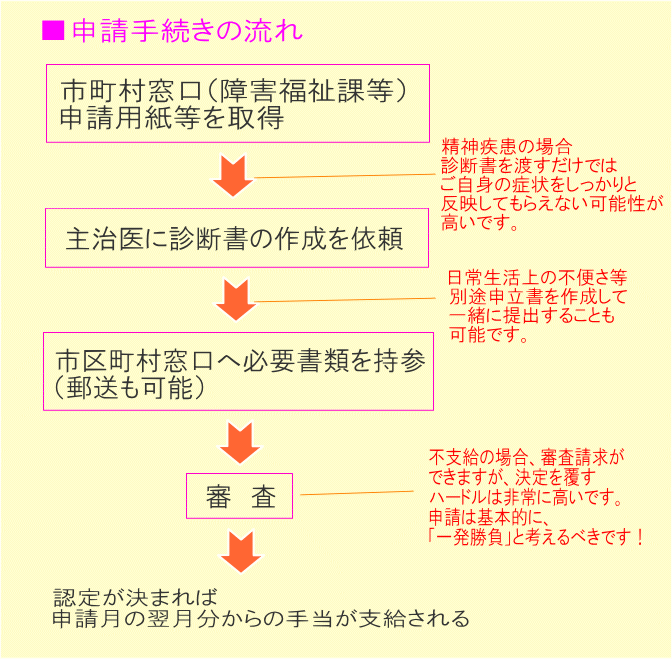
支給額 月額29,590円(2025年度の額)
支給月 原則として、毎年2月、5月、8月、11月に
それぞれの前月分までの手当が支給されます。
申請者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以上の場合には、手当を受けることができません。
**扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。

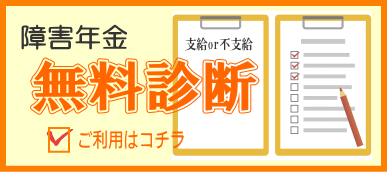
20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方が対象です。
① 別表1の障害が重複しているもの
② 別表1の障害があり、かつ他の障害部位に別表2の障害が重複しているもの
③ 別表1の第3号から第5号までのいずれかの障害があり、日常生活動作評価表 の合計点数が10点以上のもの
④ 別表3のうち1又は2に該当する障害があり絶対安静が必要なもの
⑤ 別表3のうち3に該当する障害があり、日常生活能力判定表の合計点数が14 点となるもの
*所定の診断書にて審査を行うため、身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳、指定難病の認定、介護認定をお持ちでない方でも請求可能です。
< 表1 >
| 1 | ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの イ 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視 野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 28度以下のもの エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中 心視野視認点数が20点以下のもの |
|---|---|
| 2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
| 5 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
| 6 | 前各号にあげるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 7 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
< 表2 >
| 1 | 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は1眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの |
|---|---|
| 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
| 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | そしゃくの機能を失ったもの |
| 5 | 音声又は言語機能を失ったもの |
| 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの |
| 7 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は一上肢のすべての指を欠くもの若しくは一上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
| 8 | 一下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
| 9 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
| 10 | 前各号にあげるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度 以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活 に著しい制限を加えること を必要とする程度のもの |
| 11 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
< 表3 >
| 1 | 内部障害 ⑴ 心臓の機能障害(永続する障害) ⑵ 呼吸器(呼吸器系結核及び換気機能)の機能障害(永続する障害) ⑶ 腎臓の機能障害(永続する腎機能不全、尿生成異常) ⑷ 肝臓疾患(おおむね3か月以上の療養を必要とする程度の病状) ⑸ 血液疾患(おおむね3か月以上の療養を必要とする程度の病状) |
|---|---|
| 2 | その他の疾患 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある場合においては、その状態が日常生活において常時の介護を必要とする程度のもの |
| 3 | 精神の障害 日常生活において常時の介護又は援助を必要とする程度以上の病状 |

①障害者支援施設や特別養護老人ホーム等に入所されている方
3カ月未満のショートステイ、グループホーム、有料老人ホームは問題ありません。
その他、支給対象となる施設あり
②病院または診療所に,継続して3か月を超えて入院している。
・特別障害者手当認定請求書(本人名義の口座の記入が必要になります)
・所得状況届
・代理権付与証明書
・入院、施設入所調
・所定の診断書
・年金・恩給を受給されている方は、年金額がわかるもの
※7月から12月に申請される方は昨年1月~12月の支給額がわかるもの
※1月から6月に申請される方は一昨年1月~12月の支給額がわかるもの
・対象者の口座内容が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
*詳細は市役所へお問い合わせください。
審査が厳しく、基本的に、障害年金が1級でも特別障害者手当が不支給となることが多いのが実情です。
認定基準が複雑で重複して障害が2つ以上存在しないと対象にならないと勘違いしている担当者もいます。相談に行ったのに請求書類をもらえなかったといった話も聞きます。
「精神障害やその他の疾患で診断書の実では認定が困難な場合には、療養の経過、日常生活の状況の調査、検診等を実施たうえでその結果に基づき認定する」旨記されていますが、必ずしも役所主体の調査実施される保証はありません。後で後悔することがないように、そもそも、最初に申請をする際に、診断書とは別にご自身の症状を伝える申立書を添付する等の工夫が必要です。
特別障害者手当の申請は、障害年金を取り扱っている社会保険労務士であっても、行政書士資格を持っていないとすることができません。
当事務所はダブルライセンスを所持しておりますので、障害年金だけでなく特別障害者手当の手続きについても代行させていただくことが可能です。
「少しでも受給確率を上げたい!」とお考えの場合は、あれこれとお悩みになる前に、まずはお気軽にご相談下さい。

直接面談を希望される場合、対象エリアは片道2時間迄(公共交通機関を使って)が限度です。それより遠方の地域にお住いの場合は、郵送で申請を行うことになります。
万が一、お住まいの地域にある市町村役場が郵送での対応を「不可」としている場合は、ご依頼者もしくは身近で支援して頂ける方に役所に出向いていただき、申請の手続きをして頂く必要があります(書類作成は当事務所で行います)。
両上肢の機能障害
両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能障害
両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能障害
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するものが該当します。
内部障害(心臓の機能障害)
心臓の機能障害については、永続する機能障害(将来とも回復する可能性がないか極めて少ないもの)が対象となります。
内部障害(呼吸器の機能障害)
呼吸器の機能障害については、永続する機能障害をいうものとする。
内部障害(腎臓・肝臓・血液疾患)
じん臓の機能障害については、永続するじん機能不全、尿生成異常をいうものとする。
精神の障害
ア 精神の障害は、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、気分(感 情)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害に区分し、その傷病及び状態像が令別表第2第7号に該当すると思われる症状等には、次のようなものがある。
(イ) 統合失調症型障害及び妄想性障害
|
「障害児福祉手当及び特別障害や手当の障害程度認定基準について」より
(ア) 視力の測定については、1の (1)のアによること。
㋐ 「両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.07以下のものをいう。
㋑ 「1眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。
(イ) 次のいずれかに該当する場合には、第 10 号その他疾患に該当するものとする。なお、視野の測定については、1の(1)のイによること。
㋐ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
㋑ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
聴力レベルの測定については、1の⑵のア(ただし書を除く。)、イ及びウによること。
(ア) 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものとする。(イ) 平衡機能の極めて著しい障害とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめき、手すりによる歩行のみが可能なものとする。
(ア) そしゃく機能障害は、下顎骨の欠損、顎関節の強直又はそしゃくに関係のある筋、神経の障害等により起こるものとする。
(イ) そしゃく機能を欠くものとは、歯を用いて食物をかみくだくことが不能であることによって流動食以外は摂取できないもの、食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、又はそしゃく機能障害若しくは嚥下困難のため、1日の大半を食事についやさなければならない程度のものとする。
(ア) 音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいい、構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が含まれる。
㋐ 構音障害又は音声障害
歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態のものをいう。
㋑ 失語症
大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいう。
㋒ 聴覚障害による障害
先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや、中途の聴覚障害によって発音に障害が生じた状態のものをいう。
(イ) 「音声又は言語機能を失ったもの」とは、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや、聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。
(ウ) 構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発音不能な語音を評価の参考とする。発音不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査等が行われた場合はその結果を確認する。
㋐ 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
㋑ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
㋒ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
㋓ 軟口蓋音(か行音、が行音等)
(エ) 失語症については、失語症の障害の程度を評価の参考とする。失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認する。(オ)
失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定する。
(カ) 喉頭全摘出手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、「音声又は言語機能を失ったもの」に該当するものと認定する。
(キ) 歯のみの障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により判定する。
(ク) 音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、この場合には、第4号及び第5号の障害を重複して有することがある、また、音声又は言語機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存することが多いが、この場合についても、第5号と第6号から第9号まで、又は第11号の障害のうちいくつかを重複して有することがある。
(ア) 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したものとは、両上肢のおや指及びひとさし指の各々の関節の可動域が10度以下のものとする。
(イ) 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くものとは、少なくとも必ず両上肢のおや指を欠き、それに加えて両上肢のひとさし指を欠くものである。この場合の指を欠くものとは、それぞれの指を近位節(指)骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。
(ア) 1上肢の機能に著しい障害を有するものとは、おおむね肩、肘及び手の3大関節中いずれか2関節以上が用を廃する程度の障害を有するものとする。この場合において、関節が用を廃する程度の障害を有するとは各々の関節が強直若しくはそれに近い状態(可動域10度以下)にある場合又は関節に目的運動を起こさせる筋力が著減(徒手筋力テスト2以下)している場合で日常生活動作に必要な運動を起こし得ない程度のものとする。
なお、肩関節については、前方及び側方の可動域が30度以下のものはその用を廃する程度の障害に該当するものとする。
(イ) 1上肢の全ての指を欠くものとは、それぞれの指を近位節(指)骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。
(ウ) 1上肢の全ての指の機能を全廃したものとは、1上肢の全ての指の各々の関節の可動域が10度以下のものとする。
(ア) 1下肢の機能を全廃したものとは、1下肢の股、膝及び足の3大関節のいずれの関
節とも用を廃する程度の障害を有するものとする。この場合において、関節が用を廃
する程度の障害を有するとは、各々の関節が強直若しくはそれに近い状態(可動域1
0度以下。なお、足関節の場合は5度以下。)にある場合又は下肢に運動を起こさせ
る筋力が著減(徒手筋力テスト2以下)している場合で起立歩行に必要な動作を起こ
し得ない程度のものとする。(イ) 大腿の切断の部位及び長さは実用長をもって計測するものとする。
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するものとは、室内においては、つえ、松葉づえその他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度又は片脚による起立保持が全く不可能な程度のものとする。
(ア) 内部障害
㋐ 心臓の機能障害については、1の(6)のアの(ウ)の㋐から㋙のいずれかの所見があり、かつ、家庭内での極めて温和な活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状又は狭心症症状が起こるものとする。
㋑ 呼吸器(呼吸系結核及び換気機能)の機能障害については、次のいずれかの所見があり、かつ、ゆっくりでも少し歩くと息切れがするものとする。
a 指数(予測肺活量1秒率)が30以下のもの
b 動脈血ガス分析値が動脈血 O2分圧で75mmHg 以下のもの又は動脈血 CO2分
圧46mmHg 以上のもの
㋒ じん臓の機能障害については、じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分未満、血清クレアチニンが5mg/dl 以上又は血液尿素窒素が40mg/dl
以上であって、次のいずれか2以上の所見があり、かつ、家庭内での極めて温和な活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるものとする。
a 腎不全に基づく末梢神経症
b 腎不全に基づく消化器症状
c 水分電解質異常
d 腎不全に基づく精神異常
e X線上における骨異栄養症
f 腎性貧血
g 代謝性アチドージス
h 重篤な高血圧症
i 腎疾患に直接関連するその他の症状
㋓ 肝臓疾患については、次のaに定める検査成績を示すものとする。
a 次表に掲げる肝機能異常度指表の検査成績のうち中等度又は高度の異常を3つ
以上示すもの
㋔ 血液疾患
血液疾患については、貧血、感染、発熱、各種臓器組織での出血性病変等の病状が継続するものであって、かつ、次表に掲げる血液検査異常度指表の3系列のうち1系列以上の検査成績が、異常を示すものとする。
(イ) その他の疾患
その他の疾患については、前各項に掲げるもののほか身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある場合において、その症状が(1)の表に掲げる障害と同程度以上であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この場合の障害程度の判定においては一般状態が次に該当するものとする。
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助を必要とし、日中の50パーセント以上は就床している。
精神の障害については1の⑻のアの症状を有するもの又はこれに準ずる程度の症状を有するものであって、1の⑻のエの日常生活能力判定表の各動作及び行動に該当する点を加算したものが8点以上のものとする。
なお、知的障害の程度については、標準化された知能検査による知能指数がおおむね35以下に相当する場合に該当するものとする。
補足資料
令別表第2第6号について
肝機能異常度指表
昏睡度分類
血液異常度指表
血液異常度指標(表3)

1. 「他法優先」の原則
ケースワーカーから、なぜ申請を勧められるのか?
生活保護には、他の制度で受けられる給付を優先的に受けるという「他法優先」の原則があります。そのため、障害年金をもらえる可能性がある方は、ケースワーカーから申請するように指導(指示)されることが一般的です。これは「生活保護を切るため」ではなく、制度を正しく適用するためのステップです。
2. 受給額の計算と「障害者加算」
障害年金を受給すると、その全額が「収入」として認定され、その分だけ生活保護費が減額されます。
【計算のイメージ】
生活保護費(最低生活費) - 障害年金額
= 実際に支給される保護費
しかし、障害年金(1級または2級)が認定されると、生活保護に「障害者加算」がつきます。
メリット: 年金額が引かれても、加算がつくことで結果的に世帯全体の受給総額(手元に残るお金)が月額1.5万〜2.5万円ほど増えるケースが多いです。注意点: 精神障害者保健福祉手帳の場合、障害年金3級では「障害者加算」がつかないため、手元に残る総額は変わらないことがほとんどです。
| <注意点> 多くの自治体では、精神障害者保健福祉手帳(1・2級)があれば、障害年金を受給していなくても生活保護などの「障害者加算」が支給されることがあります。 加算を受けている人が、新たに障害厚生年金を請求する際には以下のリスクがあります。 手帳が2級であっても、障害厚生年金の審査では「3級」と判定されるケースがあります。 障害者加算の判定において、手帳の等級よりも「年金の等級」が優先されるルールがあるため、年金が3級になると、それまで手帳2級を根拠に受けていた障害者加算が打ち切られることになります。 |

3. 最大の難関「遡及(そきゅう)請求」と返還義務
過去に遡って数年分の年金が一括で入る「遡及請求」が認められた場合、非常に注意が必要です。返還義務: 遡及分として受け取ったお金のうち、生活保護を受けていた期間と重なる分は、「生活保護法第63条」に基づき自治体へ返還しなければなりません。トラブル回避: 振り込まれた大金を見て「自由に使っていいお金だ」と誤解し、使い込んでしまうと、後から自治体から高額な返還請求が届き、生活が破綻するリスクがあります。入金があったら、まずは手を付けずにケースワーカーへ報告することが鉄則です。
4. 障害年金を受給する「隠れたメリット」
金額面以外にも生活保護受給者が障害年金を持つメリットは大きいです。
将来的に体調が回復して就労し、生活保護を脱却した場合でも、障害年金は(更新で認められる限り)継続して受給できます。
生活保護は資産の保有に厳しい制限がありますが、障害年金にはその制限がありません。
「国から障害の状態を認められた」という事実は、ご本人にとって大きな心の支えになることがあります。

①事前にケースワーカーに相談する
無断で申請して事後報告になると「収入隠し」と疑われるリスクがあります。
② 診断書費用の公費負担を確認する
自治体によっては、障害年金申請のための診断書代を生活保護の「検診料」として支給(経費認定)してくれる場合があります。
*経費認定をしてもらえるか事前確認を
診断書作成料等、先に本人が負担し、後日障害年金の受給権を得た場合にかかった経費分を負担してもらえる場合があります。この場合、不支給決定となった場合は持ち出しとなる可能性があります。
③専門家(社労士)の活用を検討する
生活保護受給中の方は、書類作成の負担が重荷になりがちです。また、返還金の計算など複雑な面もあるため、専門家への依頼がスムーズです。
*社労士い支払う報酬も経費負担してもらえるかどうか事前確認が必要です。
「将来的に就職し、生活保護からの自立を目指している方こそ、就労支援施設での活動と並行して障害年金の受給を検討してみませんか? 仕事を始めたばかりの時期は体調も不安定になりがちですが、障害年金という『安定した土台』があることで、無理のないペースで社会復帰へのステップを上っていくことができます。」

障害の程度が重くなった場合は、年金額の改定請求の手続きを行うことができます。障害の程度が重くなり、上位等級に該当する場合は、請求月の翌月分から年金額が増額改定されます。
ただし、過去1年以内に障害の等級が変更された方または年金額の改定請求を行った方はこの請求はできません。(省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。)
額改定請求をすることで年金額が増額されます。
障害年金は等級が決まると1~5年の期間を設けて行われる更新の手続きまでは変わる
ことはありません。もしこの間に障害の状態が悪化した場合、本人から請求の手続きを
行わない限り障害等級の変更されません。
額改定請求には、請求日前3か月以内の現症の診断書が必要です。
額改定は次の1・2の場合請求することができます。
年金を受ける権利が発生してから1年を経過した日
障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
ただし、以下の場合には、1年を経過していなくても額改定請求ができます。
1年を待たずに額改定ができる場合(新法用)>>
1年を待たずに額改定ができる場合(旧法用)>> (日本年金機構公式サイトへ)
3級の障害厚生年金を受けている人が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求
はできません。例外として、過去に支給事由を同じくする障害年金で1級又は2級に
該当したことのある人は、65歳を超えても額改定請求を行うことが可能です。
障害年金をまだ受けたことがなく不支給決定を受けた場合です。
障害認定日の時点での障害の状態が、障害等級に該当する程度でなかったとしても、
その後症状が悪化し、障害等級に該当する程度になれば、事後重症請求が可能です。
請求の翌月から障害年金を受け取ることができます。ただし、65歳に達する日の前日
までに請求しなければなりません(老齢年金の繰り上げをしている場合は事後重症請求
できません)。
特別支給の老齢厚生年金で障害者特例を受けている方は、障害状態確認届の提出が
求められませんので、2級に一度もなったことがない3級受給権者が2級程度の障害状態
になったときは、自分で65歳前に増額改定請求を行う必要があります。でないと、
その後障害の状態が悪化しても二度と2級以上の障害年金は受給できなくなります。
*旧厚年法の障害厚生年金については、等級にかかわらず65歳以後でも額改定が
可能です。
●減額改定後の額改定請求
減額改定があった場合診査日は指定日の属する月の3か月後の初日となります。
例:4月生まれの方は3か月後の7月1日が診査日となるため、額改定請求ができるのは
翌年の7月2日以後となります。
●増額改定後の額改定請求
増額改定があった場合の診査日は指定日の属する月の初日です。
例:4月生まれの人が指定日までに障害状態確認届を提出してその結果増額改定があった
場合の診査日は4月1日となります。
その後さらに障害の程度が増進した場合、額改定請求を行えるのは翌年の4月2日
以後です。
●障害状態確認届で等級が同じもしくは変更になった場合
等級に変更がなかった場合、1年を待たずにいつでも額改定請求ができます。
下の等級に落ちてしまった場合は1年を待たなければなりません。
以上、支給停止中の障害の増進、障害状態が変わったことによる額改定請求については、
請求可能な時期及び一人一人の置かれた状況でとるべき最良の手段が異なってきます。
いろいろとクヨクヨお悩みになる前に一度ご相談ください。
*支給停止の解除等は、に添付する診断書の現症日まで遡りますので悩んでいる期間が
長いほど受給できたであろう年金額が減っていきます。
*利用上のご注意
リンク先は日本年金機構HPとなります。リンク先サイト上の文章や画像などの各
ファイル、およびその内容は、予告なしに変更または中止される場合があります。
また、いかなる場合であっても、リンクに関して発生した損害について、障害年金請求
サポートセンターでは一切の責任を負わないものとします。
障害年金には、「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。
「有期認定」の場合1年から5年ごとに診断書を提出しなければなりません。その時に提出する診断書のことを障害状態確認届といいます。障害状態確認届は、誕生月の3か月前の月末にご自宅に郵送されます。提出期限は誕生日月の末日(指定日)です。
4~5か月ほどで等級に変更がなければ「次回診断書提出年月のお知らせ」が届きます。等級に変更があれば「支給額変更通知書」が届きます。
○提出指定日までに確認届を提出
・増額改定された場合
指定日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。
・減額改定された場合
指定日の属する月から3か月経過した日の翌月から減額された年金が支給されます。
| 「支給停止」の場合、再度、認定基準に該当する症状となった時には、診断書と一緒に、「支給停止事由消滅届」を提出する必要があります。 |
|---|
*提出期限は誕生日月の末日です。

令和2年6月22日 年管管発0622第8号)
「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取り扱いについて」
これまでは障害状態確認届を提出期限内に提出できず3か月が経過した場合、4ヶ月後以降に支払われるはずの障害年金の支払いが差し止められていました。
上記令和2年の通知では、過去の障害状態確認届が提出不可能でも「障害状態の継続性を医学的に推認可能」なケースでは、支払い差し止めの解除を認めるとしたことです。医学的に推認可能な期間は、同じ障害等級で年金が支払われることになります。
現症日が、提出期限の翌日以降1年以内にある場合については、当該障害状態確認届に記載された現症日に応じて、障害等級継続、増額改定、減額改定、支給停止、支給継続、失権といった審査結果が反映されるまでの期間分の年金給付について、次のとおり取り扱うこと。
○当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降3ヶ月以内にある場合
(当該障害状態確認届が提出期限の翌日以降1年以内に提出された場合に限る。)
・増額改定又は従前と同様・・・現症日の属する月の翌月から
・減額改定又は支給停止・・・指定日の属する月から3か月経過した日の翌月から

○当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日から3ヶ月を超え1年以内 にある場合
(当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降3か月以内にあって、かつ、当該障害状態確認届が提出期限の翌日から起算して1年を経過した日以降に提出された場合も含む。)
・増額改定又は従前と同様・・・現症日の属する月の翌月から
・減額改定又は支給停止・・・指定日の属する月から3か月経過した日の翌月から
当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日以降の場合(当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降3か月以内にあって、かつ、当該障害状態確認届が提出期限の翌日から起算して1年を経過した日以降に提出された場合も含む。)は、従前の障害状態及び審査結果反映後の取扱いを踏まえつつ、提出された障害状態確認届の内容から、要推認期間(当該提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月(当該障害状態確認届が提出期限の翌日から起算して1年を経過した日以降に提出された場合にあっては、提出期限の属する月の翌月)から、当該現症日の属する月までの期間をいう。)における障害状態の継続性を医学的に推認できるかどうかを検討すること。その上で、当該検討結果に沿って、要推認期間分の年金給付について、次の取扱いを行うこと。 ① 障害状態の継続性を医学的に推認できる場合は、要推認期間分の年金給付 について、一時差止を解除し、従前の障害等級が継続するものとして取り扱 うこと。 ② 障害状態の継続性が推認できない場合は、要推認期間分の年金給付につい て、一時差止の解除を行わないものとすること。 |
|---|
○提出期限の翌日を始期とした1年を単位とする期間についてそれぞれ障害状態確認届 の提出がある場合
各年の確認届の現症日の翌月から遡及して額改定、支給停止を行われる。
○提出期限の翌日を始期とした1年を単位とする期間についてそれぞれ障害状態確認届 の提出が無い年がある場合
・確認届の提出がある年は、その内容に従って額改定、支給停止が行われる。
・確認届の提出がない場合は、前後の障害状態の継続の有無について医学的に推認で きるかどうか検討。
*前と後で等級が変わらない場合・・・従前の等級とする
確認届を提出できない期間(要推認期間)がある場合は、要推認期間における障害状態の継続性を医学的に推認できるかどうかを検討。 ① 障害状態の継続性を医学的に推認できる場合は、要推認期間分の年金給付につい て、一時差止を解除し、従前の障害等級が継続するものとして取り扱うこと。 ② 障害状態の継続性が推認できない場合は、要推認期間分の年金給付について、一 時差止の解除を行わないものとすること。 |
|---|
なお精神疾患の場合には、病気の性質上、医学的な推認はなされないようです。

眼の障害
白内障、緑内障、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、ぶどう膜炎、視野狭窄眼球委縮、網膜脈角膜委縮、網膜はく離、両錐体ジストロフィー、黄斑変性症、レーベル視神経症、ベーチェット病(眼に症状が出る場合)、多発性硬化症(眼に症状が出る場合)、外傷性網脈絡破裂・眼球破裂、低酸素脳症による失明など
聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害
感音性難聴、特発性難聴、メニエール病、真珠腫性中耳炎、音響外傷、内耳障害、失語症、咽頭腫瘍、上顎腫瘍、舌腫瘍、舌がん、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出や脳梗塞による言語機能の消失など
肢体の障害
上肢・下肢障害、脳梗塞・脳出血後遺症、脳血管疾患、脳腫瘍、脳挫傷、頭部外傷後遺症、脊髄小脳変性症、頚椎症性脊髄症、頸髄損傷、パーキンソン病、脊柱管狭窄症、筋ジストロフィー、ヘルニア、慢性関節リウマチ、悪性関節リウマチ、変形性股関節症、膝関節屈曲位拘縮、人工関節、人工骨頭、脳性麻痺、頚椎性麻痺、腰椎分離すべり症、大腿骨頭壊死、上肢・下肢・指の切断、糖尿病性壊疽、糖尿病性神経障害、多発性骨髄腫、多発性硬化症(肢体に症状が出る場合)、線維筋痛症、多系統萎縮症(オリーブ小脳萎縮症)、アルコール性末梢神経障害、脳脊髄液減少症、ポリオ、ポストポリオ、膠原病、ジストニア、ミトコンドリア脳筋症、筋委縮性側索硬化症(ALS)、脊柱管狭窄症、骨肉腫(骨のがん)、ミエロパチー、ビュルガー氏病、ホジキン病、皮膚筋炎、全身性エリテマトーデス(SLE)、胸椎黄色靱帯骨化症、後縦靭帯骨化症など
精神の障害
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、気分障害、発達障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム)、アルコール依存症、知的障害、ダウン症、てんかん、高次脳機能障害、非定型精神病、若年性アルツハイマー、認知症、トゥレット症候群(チック症)など
※障害年金では認定の対象外としている「神経症」や「人格障害」で認定された事例
強迫性障害
呼吸器疾患の障害
中皮腫、肺気腫、間質性肺炎、肺結核、肺線維症、慢性閉塞性肺疾患、肺がん、じん肺、肺胞のう症、気管支喘息、気管がん、気管支炎、気管支拡張症、非結核性抗酸菌症、慢性呼吸不全、酸素療法など
循環器疾患の障害
心不全、ファロー四微症、ペースメーカー装着、心室中隔欠損、人工弁装着、拡張型心筋症、心臓弁膜症、大動脈弁狭窄症、大動脈弁精査不全症、梗塞型心筋症、狭心症、心筋梗塞、心房細動、心室細動、心室頻拍症、洞不全症候群、冠動脈バイパス術後遺症、高度房室ブロック、完全房室ブロック、モビッツⅡ型房室ブロック、僧房弁狭窄症、相貌弁膜症、悪性高血圧症、解離性大動脈瘤、マルファン症候群、ロイス・ディーツ症候群など
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
人工透析、腹膜透析、慢性腎不全、糖尿病性腎症、慢性腎炎、慢性糸球体腎炎(ループス腎炎)、腎機能障害、IgA腎症、ネフローゼ症候群、腎のう胞、肝のう胞、肝硬変、肝腫瘍、肝臓がん、肝細胞がん、糖尿病など
血液・造血器・その他の障害
悪性新生物(がん)(前立腺がん、胃がん、大腸がん、直腸がん、乳がん、子宮体がん、卵巣がん、肛門がん、悪性リンパ腫、後腹膜平滑筋肉腫など)、人工肛門、骨髄腫、脳腫瘍、HIV(エイズ)、ヒト免疫不全ウイルス感染症、白血病、血友病、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、再生不良性貧血、好酸球性多発血管炎性肉芽腫、自己免疫疾患、骨髄異形成症候群、慢性炎症性脱髄性多発性神経症(CIDP)、キャッスルマン病、多発性骨髄腫、化学物質過敏症、電磁波過敏症、クローン病、バセドウ病、膠原病、潰瘍性大腸炎、サルコイドーシス、シェーグレン症候群、ギラン・バレー症候群、慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)、慢性群発頭痛、原発性免疫不全症候群(分類不能型免疫不全症CVID)など
障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。
(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)障害年金裁定請求書
診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などです。当然のことながら、診断書は医師にしか作成することができません。障害年金の成否の大部分は診断書で決まります。
病歴・就労状況等申立書(申立書)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価しアピールできるのは、この申立書以外にないので、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。但し、現状、等級審査において診断書程重要視されてはおらず、診断書との整合性に注意をしつつ、上げ足を取られないようにする必要があります。万が一、自身について不利な情報を記載した場合は、不服申し立て修正、訂正することはほぼ不可能です。
受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。

| 障害給付 請求事由確認書 「認定日請求が認められなかった場合には、事後重症請求を行います」という意思を示すものです。この書類は遡及請求の際に提出を求められるます。 *この際の遡及請求を主位的請求、認定日請求を予備的請求と呼びます。 |
|---|
| 年金裁定請求の遅延に関する申立書 障害年金の請求が、本来の受給権発生日(障害認定日)から大幅に遅れた場合に、その遅延の理由を説明し、時効による年金給付の消滅について理解していることを確認するための書類です。 |
| 障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書 同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合に、以前提出して初診日として認められた証明書類(受診状況等証明書など)を、今回の請求でも利用したいと申し出るための書類です。 |
| 障害年金の初診日に関する調査票 初診日を特定する目的で、年金事務所(または日本年金機構)から提出を求められることがある追加の書類(アンケート形式)です。 これは、通常の初診日証明書類(受診状況等証明書など)に加えて提出を求められるもので、特に初診日が遡及しやすく、特定が難しい傷病について、発病から初診までの経緯や自覚症状を詳しく確認するために使用されます。 調査票の提出が求められる主な傷病 先天性障害(眼用、耳用など) 先天性股関節疾患 糖尿病 腎臓・膀胱の病気 肝臓の病気 心臓の病気 肺の病気 |
障害給付 請求事由確認書
| 眼の障害 | ブドウ膜炎、緑内障、白内障、眼球萎縮、 網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、 腎性網膜症、糖尿病網膜症等 |
|---|---|
| 聴覚障害 | 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病 |
| 鼻腔機能障害 | 外傷性鼻科疾患等 |
| 平衡機能障害 | メニエール病、脳疾患後遺症等 |
| そしゃく・ 嚥下機能障害 |
顎・顎関節・口腔・咽頭・喉頭の欠損、 重症筋無力症、筋ジストロフィー、 筋委縮性側索硬化症等 |
| 音声・言語機能障害 | 咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)等 |
| 上肢の障害 下肢の障害 体幹・脊柱の機能障害 肢体の機能障害 |
人工骨頭等、骨折、変形性股関節症、 肺髄性小児麻 脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、 脳軟化症、くも膜下出血、 脳梗塞、上肢または下肢の切断障害、 重症筋無力症、脳出血 上肢または下肢の外傷性運動障害、 関節リウマチ、ビュルガー病、 進行性筋ジストロフィー ポストポリオ症候群等 |
| 精神の障害 | うつ病、そううつ病、統合失調症、てんかん、 知的障害、発達障害、高次脳機能障害等 |
| 神経系統の障害 | 脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)、脳腫瘍、 多発性硬化症、パーキンソン病、脊髄損傷、 脊髄腫瘍、糖尿病等 |
| 呼吸器疾患による障害 | 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、 膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全等 |
| 心疾患の障害 | 弁疾患、心筋疾患、虚血性疾患(心筋梗塞、 狭心症) 難治性不整脈、大動脈疾患、 先天性心疾患等 |
| 腎疾患の障害 | 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、 ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎等 |
| 肝疾患の障害 | 肝炎、肝硬変、肝がん等 |
| 血液・造血器疾患による障害 | 再生不良性貧血、溶血性貧血、 血小板減少性紫斑病、 凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種 多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症等 |
| 代謝疾患の障害 | 糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、 糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽等 |
| 悪性新生物 による障害 |
すべての悪性腫瘍 |
| 高血圧症による障害 | 悪性高血圧症等 |
| その他の疾患 による障害 |
直腸腫瘍、膀胱腫瘍、化学物質過敏症、線維筋痛症、 慢性疲労症候群、脳脊髄液減少症、クローン病、 ヒト免疫不全ウイルス感染症等 |
認定基準については、リンクの転送先は日本年金機構公式サイトとなります。
*利用上の注意
リンク先は日本年金機構HPとなります。リンク先サイト上の文章や画像などの各ファ
イル、およびその内容は、予告なしに変更または中止される場合があります。また、
いかなる場合であっても、リンクに関して発生した損害について、障害年金請求サポー
トセンターでは一切の責任を負わないものとします。

| 「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。 |
|---|
1年6カ月前に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至ったと認められた場合は、症状固定日が障害認定日になります。
症状固定については、平成24年9月に認定基準が改正され以下のようになりました。
| 「傷病が治った場合」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又はその症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。 |
|---|
下記の状態になった場合、1年6か月以内であってもそれぞれの日が障害認定日として扱われます。
○人工透析療法を受け始めてから 3か月経過した日、かつその日が初診日から
1年6か月以内の場合。
○人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日
| 肘関節の上腕尺骨関節に人工関節を挿入置換した場合3級 *上腕橈骨関節の橈骨頭に人工骨頭を挿入置換した場合は、該当しない |
○肢体を離断・切断した障害は、原則として切断・離断した日
| 障害手当金の場合は、創面が治癒した日 |
○脳血管障害は初診日より6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復が 殆ど望めないと認められるとき。
(初診日から6か月が経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ)
| *診断書の備考欄に機能回復が見込めないこと、医学的リハビリを行っていないこと、ボツリヌス注射は症状の改善を目的としたものではないこと等 を記載してもらうこと。 ※精神疾患の高次脳機能障害は1年6か月を待つ必要あり |
○人工心臓、補助人工心臓心臓移植を移植した日・装着日で1級認定。
但し、1~2年後に症状が安定した場合は級が下がる場合あり。
○心臓ペースメーカー、 植え込み型除細動器(ICD)、人工弁、CRT(心臓再同 期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)を装着した日。
○人工血管(ステントグラフトを含む)を 挿入置換した日。
但し3級該当は、診断書の一般状態区分表が「イ」又は「ウ」の場合。
| *心臓にステントを入れているだけで障害年金対象になるのは(大動脈疾患)です。胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入している場合には障害年金3級となります。 胸部大動脈瘤に対しては、胸部・胸腹部に置換した場合は該当するが、腹部に置換した場合は該当せず。 人工血管は腕や頸動脈に置換しても該当しません。 冠動脈へのステント留置術も該当せず。 |
○人工肛門を造設した場合や尿路変更術を 施した場合、手術日から起算して 6か月を経過した日
| 人工肛門造設日から起算して6か月経過前後に閉鎖した場合 ⇒6カ月経過目の閉鎖は、障害認定日の特例にならない ⇒再度造設した場合は、再度造設した日から起算する |
○新膀胱造設日
○喉頭全摘出した日
○常時(呼吸)在宅酸素療法を開始した日
筋萎縮性側策硬化症(ALS)による四肢・体幹の筋萎縮・筋力低下によって呼吸困難となり 、 入院中から24時間のNPPV(非侵襲的間欠陽圧人工呼吸療法)を開始した場合も認められる可能性大。
○今後の回復は期待できず、初診日から6ヵ月経過した日以後において、気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。
○遷延性意識障害(植物状態)の状態に 至った日から起算して3月を経過した日以後、医学観点から、機能回復が殆ど望めないと認められたとき。
| 起算日は初診日からではなく、遷延性意識障害の状態に至った日から起算。 *診断書又は受診状況等証明書には起算日の明記が必要。 |

| 障害認定日とは 障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。 |
上記以外でも「傷病が治った場合」に該当すれば、初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日として認定することは可能とはなっていますが、実際のところ、年金機構が掲げている障害認定日の特例以外で、1年半前に症状固定とされる事例はほとんどないと言えるのではないでしょうか。
症状固定を主張し、無理くりで請求書を提出しても、、障害認定日未到来で却下になる可能性が高いと考えられます。

初診日要件では、障害の原因となったけがや病気で初めて医療機関(医師、歯科医師 整骨院は除きます)にかかった日(初診日)に下記のいずれかに該当する必要があります。
・国民年金か厚生年金のいずれかの被保険者であること
・20歳未満
*10代で会社員や公務員になっている場合で、20歳までの厚生年金保険加入期間に「初診 日」がある人は、「障害厚生年金」の対象となります。
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
(老齢基礎年金を繰り上げしている場合は除きます)
*初診日とは・・・その病気やケガで初めて受診した医療機関のことで、
必ずしも確定診断を受けた日とは限りません。
初診日において以下の①または②を満たしている必要があります。
なお、免除期間も保険料を支払っていた期間としてカウントされます。
初診日を過ぎてから保険料を支払ったり、初診日を過ぎてから免除手続をし
ている場合はカウントされません。
① 障害年金を請求しようとする傷病にかかる初診日の前日において、初診日の
属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付期間と免除期間を
合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。
② ①を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料
納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において
65歳以上でないこと。平成38年4月1日前(3月31日まで)に初診日があること。
【20歳前障害の例外】
20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。
国民年金の保険料は20歳になってから支払いますが、20歳前に初診日が
ある人はそもそも保険料を払うことができないためです。
<重要>
*納付要件については必ず年金事務所等で確認をすることをお勧めいたします。
すべて提出書類を揃えた後に納付要件を満たしていないことが発覚した場合、書類が全て無駄になるばかりでなく、請求自体ができなくなる場合があります。
*これから医療機関への受診(あくまで初診の場合)を考えている方は、まず最初に年金の納付状況を確認しておきましょう。受診後、慌てて納付しても一切認められません。未納等がある場合は、受診前に納付しておく必要があります。
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで 判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症 状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

平成27年10月1日から障害年金の初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められるようになりました。
初診日を証明する書類の無い場合、以下の提出書類を審査のうえ、本人の申し立てた日が初診日として認められます(認められる場合があります)。
①初診日について第三者(隣人、友人、民生委員等)が証明する書類及び参考書 類が提出された場合
※ 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、以前から第三者の証明による
初診日の確認が認められています。
②保険料納付要件を満たしたうえで、初診日が一定の期間内にあることを示す参 考書類が提出された場合
| ◆<参考書類の例> 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・糖尿病手帳・お薬手帳(処方箋) 領収書・診察券(診察日や診療科が分かるもの)・問診票 身体障害者手帳等の申請時の診断書 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書 事業所等の健康診断の記録 母子健康手帳 健康保険の給付記録 小学校・中学校等の健康診断の記録・成績通知表 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書 初診日に関する第三者からの申立書 入院記録・手術記録・入院時の同意書・入院時の説明書・看護サマリー・処方箋救急搬送記録・交通事故証明書 日記帳・古いカレンダー 他 |
初診日が5年経過していてカルテが保存されていなくても、「患者サマリー」として既往歴を保存している医療機関が多くなってきています。
*患者サマリー
患者の病歴や治療・看護等の情報を要約した書類である。患者が転院または退院する際や病棟が変わる際に、次の受け入れ先(施設、家庭、別の病棟など)でスムーズなケアと継続的な看護が続けられるようにするため、看護師が作成するものです。

実際のところ第三者証明だけで初診日が認められるようなことはほぼありません。医師や看護師の協力を得られる場合を除いては、第三者証明だけでなく初診日について参考となる他の資料の提出が必須です。
年金事務所へ相談に行かれると、「初診日の証明できないようであれば第三者証明を出すように」と言われることがあります。
相談者は第三者証明さえ出せば初診日が認められると思いがちですが、それは大きな間違いです。友人、知人に書いていただいても、よほど客観的にかつ説得力のある内容でないと認められることはありません。
初診日の証明ができない場合は第三者証明に走る前に、とにかく受診した病院をどんどん遡っていき、カルテの有無を確認したうえで、カルテ内に初診日の記載がないか確認をしていく必要があります。請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(カルテ等)に本人申立ての初診日が記載されており、それをもとに作成された資料があれば、その資料単独で初診日の認定が可能となります。
記載内容の証明をお願いしても、病院からは断られることが有ります(理由は不明ですが)。その場合はカルテの開示請求をかけ障害年金請求時に添付するという方法もあります。
| 令和3年(厚)第765号裁決 いかなる症状で受診し、 どのような診療を受けたか等の具体的な記載はないのであるから、これらの申立書は、 いずれも初診日認定資料に採用することはできず、その他に請求人の申し立てを裏付ける客観的資料は存しないのであるから、 請求人の申し立てを認めることはできない。 |
|---|

令和2年度10月より、平成29年度以降に提出された受診状況等証明書は、取り直しをしなくてもいいようになりました。但し、あくまでも前回の請求で程度不該当(初診は問題なし)の場合です。
『障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書』(添付)で、初診の証明ができます。不支給通知書を添付しなければなりませんので、もし保存していなければ個人情報開示を行って入手し添付します。
年金機構ではかなり前のものまで請求書類を保存していますので、上記よりも古い初診証明でも認められる場合もあります。
*障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書 記載例
障害年金は初回の請求が非常に大切です。とりあえず出して不支給なら不服申し立てができるという発想は非常に危険です。審査請求、再審査請求まで考えた場合、請求時から2年程度はかかります。その労力は計り知れません。
障害年金は書類さえそろえば誰にでも請求は可能です。ゆえに、安易に請求をし不支給決定を受ける方が非常に増えております。
初回請求で受給権を取るために、少しでもご不安なことがございましたら、障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談ください。

知的障害や発達障害と他の精神疾患が混在しているケースについては、障害の特質性から以下の通りの扱いとなります。但し、認定にあたってはこれらを目安に発病の経過や症状から相貌的に判断されることになります。
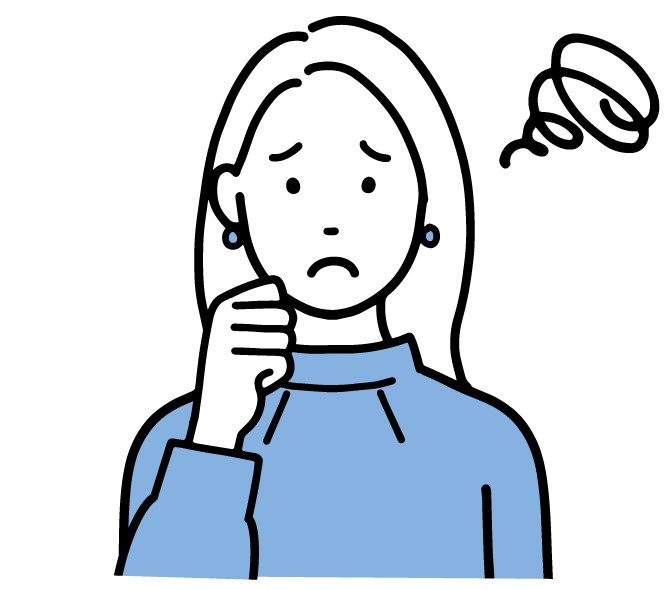
① うつ病又は統合失調症と診断されていた後に発達障害が判明する場合については、そのほとんどが診断名の変更であり、新たな疾病が発症したものではない事から同一疾病として扱います。
② 発達障害と診断された後にうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や精神病様態は、発達障害が起因して発症したものとの考えるのが一般的であることから同一疾病として扱います。
③ 知的障害と発達障害については、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが、障害年金の受給に至らない程度の場合に後から発達障害が診断され障害等級に該当した際は、原則として同一疾病として扱います。
例えば、3級程度の知的障害であった方が、後に発達障害の症状が顕著になった場合は同一疾病とし事後重症扱いとなります。
知的障害と診断された方が後にうつ病を発症した場合は、知的障害に起因して発症したと考え同一疾病として扱います。
なお、発達障害や知的障害の症状の中には、稀に統合失調症の様態を呈するものもあります。
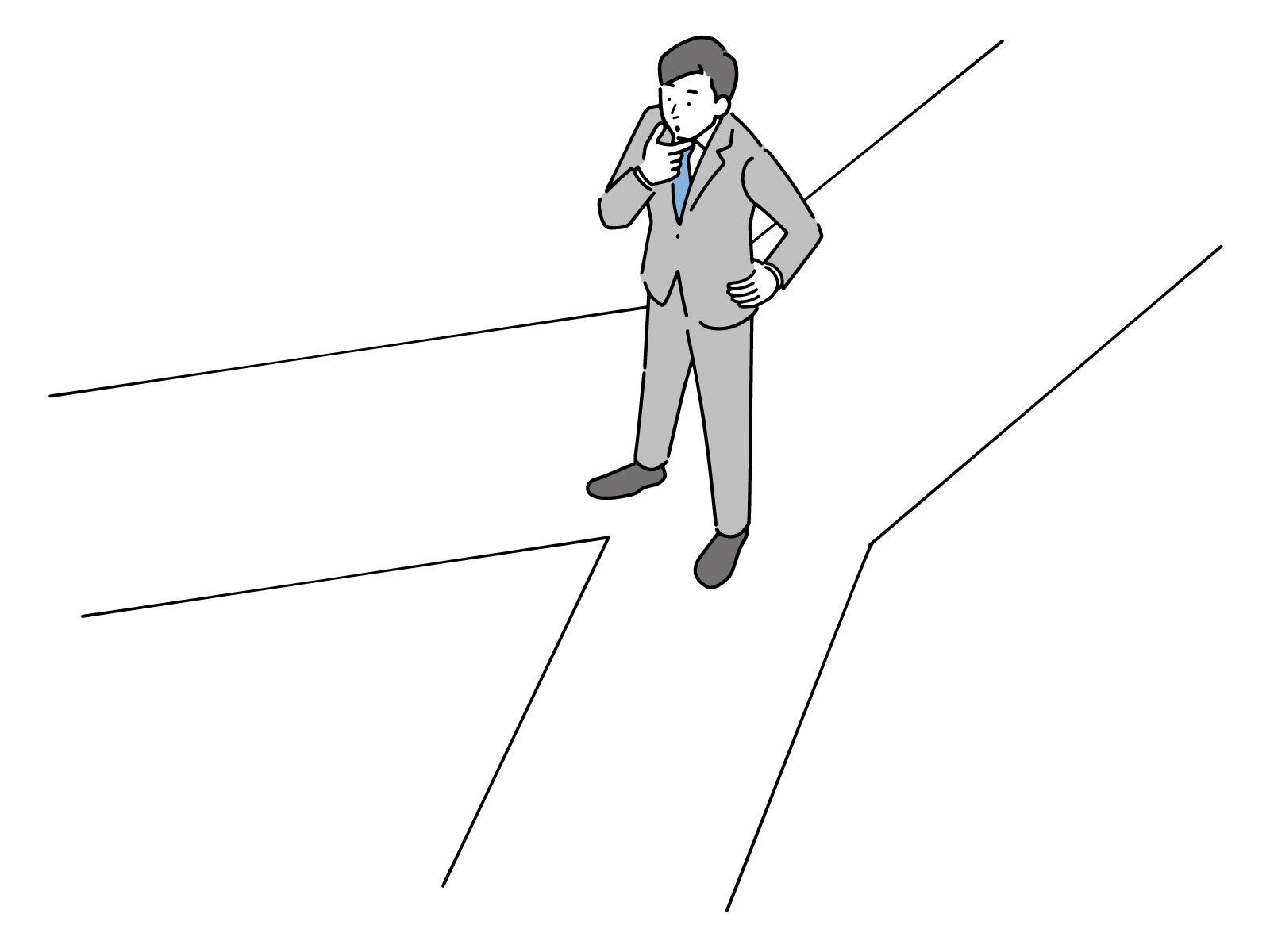
① 知的障害を伴わない又は3級不該当程度の知的障害がある方については、発達障害の症状により、初めて診療を受けた日を初診とし別疾病として扱います。
② 発達障害や知的障害である方が後に統合失調症を発症することは極めて稀とされていることから原則別疾病とされます。
③ 知的障害と診断され後に神経症で精神病様態を併発した場合は別疾病として扱います。
*但し精神病様態が、統合失調症の病態を示している場合は、統合失調症が併発したとして取り扱います。
同一疾病として扱うか、別疾病として扱うかにより、初診日や障害認定日が当然ながら変わってきます。準備書類も違ってきますので注意が必要です。

具体的な取扱いについては、厚生労働省の疑義照会「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い(情報提供)(給付企No.2011-1)」で、回答されています。
(内容)
| 前発疾病 | 後発疾病 | 判定 |
|---|---|---|
| 発達障害 | うつ病 | 同一疾病 |
| 発達障害 | 神経症で精神病様態 | 同一疾病 |
| うつ病 統合失調症 |
発達障害 | 診断名の変更 |
| 知的障害(軽度) |
発達障害 | 同一疾患 |
| 知的障害 | うつ病 | 同一疾患 |
| 知的障害 | 神経症で精神病様態 | 別疾患 |
| 知的障害 発達障害 |
統合失調症 | 前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要) |
| 知的障害 発達障害 |
その他精神疾患 | 別疾患 |
前の病気やケガが無ければ、後の疾病は起こらなかったであろうと認められる場合、その2つの傷病は「相当因果関係」ありとして、同一の傷病とみなされます。
この場合は、前の傷病における初診日が障害年金請求上の初診日として扱われます。
*もし、診断書に「傷病の原因又は誘因」、「既存障害」、「既往症」の欄に相当因果関係がありとする傷病名が記載されてある場合は、初診日が前の病気にまで遡る可能性がありますので注意が必要です。
相当因果関係があるとされている具体的な傷病については、例として下記の傷病があります。

初診日 とは、障害の原因となった傷病について、初めて 医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいいます。
*整骨院、ほねつぎ、鍼灸院等は初診日として認められません。
障害年金における初診日は、初診日にどの年金制度に加入していたかにより受給できる障害年金が異なるとともに保険料納付要件判断のもとになりますので、障害年金の請求において非常に重要な意義を持っています。

障害年金における初診日は、具体的には次のように判断されます。
○初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
※その傷病に関する診療科や専門医でなくてもかまいません。
○同一傷病で転医をした場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日。
○同一傷病で傷病が治ゆし、再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受け た日。
○傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判 断される場合は、最初に受信した日が対象傷病の初診日です。
○じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日。
○障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病がある ときは、最初の傷病について最初に受診をした日。
○先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日。
先天性心疾患、網膜色素変性症等は、具体的な症状が出現し初めて診療を受けた日。
○先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は、出生日が初診日とな り、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診 療を受けた日。
○起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師 の診療を受けた日。
*過去の傷病が治癒した、その後再び同一傷病を発症した場合は、再発と して過去の傷病とは別傷病としますが、治ゆしたと認められない場合は、 傷病が継続しているとみて同一傷病として取扱われます。
| 健康診断を受けた日(健診日)は、原則初診日として取扱いません。 ただし、 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示があった場合、または初診時(1番最初に受診した医療機関)の医師の証明が添付できない場合であっても医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めたうえで、初診日を認めることができるものとされています。 |
|---|

「相当因果関係あり」か「相当因果関係なし」かによって、以下のように初診日が変わります。
相当因果関係あり→前発の病気やケガの初診日
相当因果関係なし→後発の病気の初診日
ただし、障害年金における相当因果関係は、前発の障害が疾病またはケガの場合で、後発の障害は疾病のみとされています。
| 相当因果関係ありと判断される具体例 |
|---|
| ○糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、 糖尿病性動脈閉塞症) ○糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に疾患し、その後、慢 性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありと して扱う ○肝炎と肝硬変 ○結核の化学療法による副作用として聴力障害が生じた場合 ○手術等による輸血により肝炎を併発した場合 ○ステロイドの投薬による副作用で大腿骨無腐性壊死が生じたことが明らかな場合 ○事故または脳血管疾患による精神障害がある場合 ○肺疾患に罹患し手術を行い、その後呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発 生の期間が長いものであっても相当因果関係ありとして取り扱う ○転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であること が確認できたものは、相当因果関係ありとして取り扱う |
相当因果関係無しとして判断されるもの
○高血圧と脳出血又は脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱います。
○近視と黄斑部変性、網膜剥離又は視神経萎縮は、相当因果関係なしとして取り扱います。
○糖尿病と脳出血又は脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱います。
過去の傷病と同一の傷病を発症した場合、再発なのか社会的治癒が認められるかによって初診日が異なってきます。
再発
過去の傷病が治癒したあとに、再び同じ傷病が発症したケースをいいます。
再発した場合には過去の傷病とは別の傷病として扱われ、再発してからはじめて医師等を受診した日が初診日にあたります。
原則として初診日は、障害の原因になった傷病で初めて医師等の診察を受けた日のことですが、難病については症状が初めて出て受診した日ではなく、確定診断を受けた日が初診日になるケースもあります。
*線維筋痛症・化学物質過敏症・慢性疲労症候群・重症筋無力症については、一定の条件を満たしていれば請求者が申し立てた日を、障害年金の初診日として取り扱います。
上記のように初診日一つにしても複雑な要件が絡み合ってきます。初診日の設定を間違えると全て最初からやり直さなければなりません。
安易に請求を行医不支給になると、その後の請求が非常に困難になってきます。疑問点、ご不明な点等がありましたら当事務所にお問い合わせください。