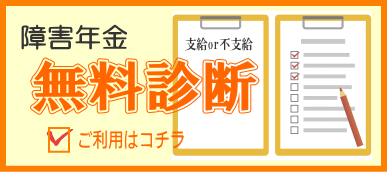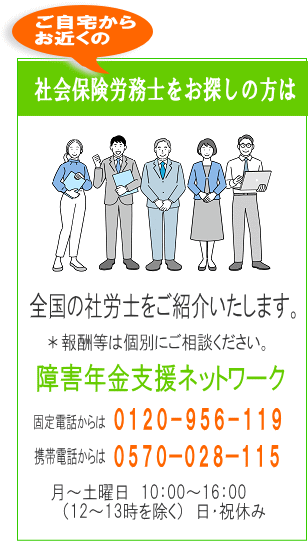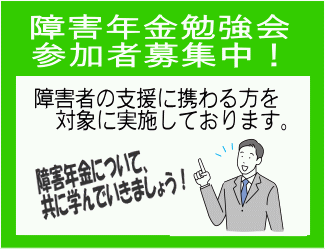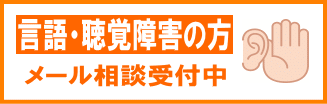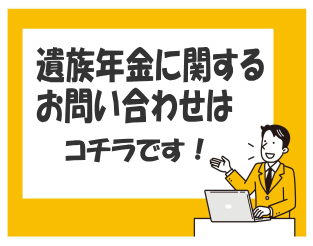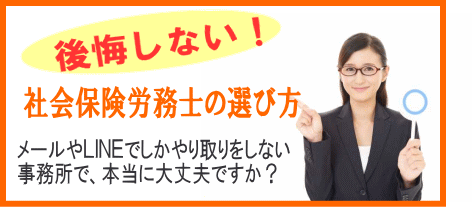社会的治癒を主張する場合
本来、障害年金の初診日は「障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日」をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
また、過去の傷病が治癒し、同一の傷病で再度発症(再発)した場合は、「再発し医師等の診療を受けた日」になります。
社会的治癒とは、医学的には治癒していない場合に、社会保険上、被保険者が不利益を受けないための考えだされた概念です。

社会的治癒について法令上の明確な定義はありませんが、いくつかの裁決例で以下のように述べられています。
| 引用:平成26年(厚)第892号 平成27年9月30日裁決 令和3年(厚)台342号 にも同様の引用あり 社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合には、「社会的治癒」を認め、治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許されるものとされており、当審査会もこれを是認している(以下省略) |
|---|
| 引用:令和3年(厚)第755号 社会保険の運用上、 いわゆる社会的治癒の概念の下に、 傷病が医学的な意味では治癒したとはいえないが、 その症状が消滅して社会復帰が可能となり、 かつ、 投薬治療を要せず、 外見上治癒したとみえるような状態が、 ある程度の期間にわたって継続した場合には、 これを治癒に準じて取り扱うことが承認されているところであるが、 当審査会では、 その適応の判断は、 それぞれの疾病の特性や個人の社会的背景に応じて取り扱うことが、 社会的治癒の理念的にふさわしいとしている。 |
|---|
| 引用:令和3年(厚)第1101号 社会保険の運用上、 過去の傷病が治癒した後再び悪化した場合は、 再発として過去の傷病とは別傷病として取り扱い、 治癒が認められない場合は、 過去の傷病と同一傷病が継続しているものとして取り扱われるところ、 医学的にば冶癒に至っていないと認められる場合であっても、 軽快と再度の悪化との間に、 いわゆる「社会的治癒」が あったと認められる場合は、 再発として取り扱われることとなるが、この社会的治癒があったと認め得る状態としては、 相当の期間にわたって症状がなく医療(予防的医療を除く。 )を行う必要がなくなり、通常の勤務に服していたことが認められる場合とされている。いわゆる「社会的治癒」については、 治癒と同様に扱い、 再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許されるものとされ、 当審査会もこれを是認しているところである。 |
|---|
医学的には治癒していなくても、社会生活を問題なく過ごせていた期間が一定以上あることが客観的に認められれば、一旦は治癒したとものとして以前と同じ疾患が再び生じても新たな傷病を発病したものとみなすという考え方です。
基本的に社会的治癒は請求者の利益を守るための概念です。本人が何も主張しなければ、原則どおりの初診日が障害年金の初診日になります。
障害年金請求において以下のような場合、社会的治癒を主張するメリットがあります。
社会的治癒を主張するメリット
- 従来の初診日では受給要件を満たすことができなかった場合
⇒社会的治癒を主張することで納付要件をクリアできることがある。
- 従来の初診日では国民年金加入だった場合
⇒社会的治癒を主張することで初診日を厚生年金加入期間に設定できる。
- 初診日がかなり前にあってカルテ等が廃棄されており、証明することが難しい場合
⇒社会的治癒を主張することで初診日証明が可能となる。

社会的治癒が認められる条件とは何か?
残念ながら、社会的治癒が認められる条件は明示されていません。
ただし、今までの判例等の積み重ねによって、以下の3条件が必要だと言われています。
病気などの治療を行う必要がない状態になったことを証明
医学的な治療を行わず安定した社会生活を送ることができ、薬等も飲んでいない状態が続いていることを証明。(病気などの経過観察や予防に関するケアを医師の判断のもとで行っている場合は、社会的治癒と認められる可能性があります)。
一定期間、社会生活を問題なく行うことができていたことを証明
就労、家事等問題なく行われており、社会生活に支障をきたしていない状態が一定期間(概ね5年以上)続いていたことを証明。また、外見上において自身も他者も、病気などが回復したと見て取れる状態であることが重要です。
*どの程度の期間があれば社会的治癒が認められていたのかについては、過去の裁決例でも確認することができません。年月日は全て伏せられているためです。
社会的治癒とは、傷病が、医学的な意味で治癒したとは言えないが、その症状が消滅して社会復帰が可能となり、かつ、治療投薬を要せず、外見上治癒したと見えるような状態がある程度の期間にわたって継続することであり、保険給付上はこれを治癒に準じて扱うことが承認されている。もっとも、治療投薬については、全くこれをしない状態であることは必ずしも必要ではなく、医事的・経過観察的な治療が継続していても社会的治癒の成立を妨げないとされる。社会的治癒と認めるのに必要な寛解期間の長さは、傷病の性質によっても異なり(たとえば癌の手術をしたような場合や精神病の場合には、ある程度長めな寛解期間が必要とされる傾向にある)、また、障害を事由とする年金給付の場合と健保法上の傷病手当金の場合戸でも、必要とされる寛解期間の長さは同じではない。 加茂紀久男『裁決例による社会保険法』民事法研究会2011,203項 |
|---|
保険者からの社会治癒の援用について
保険者から社会的治癒を持ち出して、請求者の主張する初診日を後ろにずらすようなことは認められないとされています。但し、実際には保険者が社会的治癒を援用していくる場合もあります。
病歴・就労状況等申立書、年金請求書及び診断書作成上の注意点
初診日は再発後の初診日を記入。再発後の病院で受診状況等証明書を取得
病歴・就労状況等申立書には初診日(再発前)から現在までの状況を記入
*問題なく社会生活を送れていた旨記載
診断書には寛解して、治療の必要がない期間が続いていたことを記載してもらう
社会的治癒を主張するための必要書類について
医師の診断書
医師に診断書を書いてもらう際に、過去に病気などの治療をしていけれども、それが寛解し、治療を行わないでもよい期間が続いたことなどを明確に記載してもらう必要があります。
給与明細
就労が一定期間継続しており、意欲的に働いた結果として昇給・賞与の支給があったことを証明。
厚生年金ではなく、国民年金だった場合、自営で仕事していた証明、所得証明、留学・資格取得等の証明などの根拠を出す必要があります。
その他、旅行に行った際の写真、草野球等で楽しくプレーしている写真等を収集し添付して提出することも可能です。

以上、概要を説明いたしましたが、実務的には社会的治癒の証明は困難なケースが多いです。
第三者から見ても寛解し、問題なく社会生活が遅れている状態であること数々の書類を揃え証明できるかがポイントです。
初診証明ができず、ただ単に自己判断で受診を辞め、5年経過したから社会的治癒を主張してみる、で認められる可能性は低いです。
特に就労していない場合、または就労していてもバイト程度であった場合は社会生活が問題なく過ごせているとはされないことが多いです。
社会的治癒は請求者本人を救済するための精度ですが、自力で書類を揃えたり、診断書作成のポイントを医師に説明することは非常に難しいのも事実です。一度障害年金を専門に取り扱っている社会保険労務士に相談してみることをおすすめ致します。