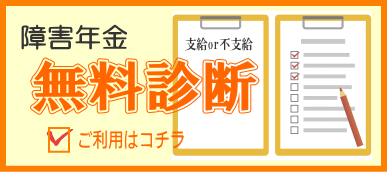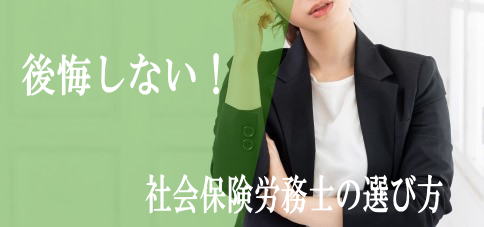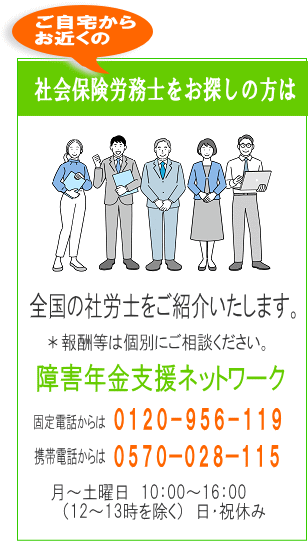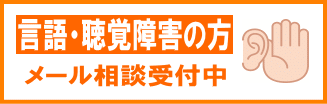認定調書の見方
障害年金請求をした結果、不支給の場合は、「国民年金・厚生年金保険の支給しない理由のお知らせ(不支給決定通知書)」が届きます。不支給決定通知書と一緒に同封された「決定の理由」と記載された書類に不支給の理由がざっくりと示されていますが、より詳細な理由をしるために障害状態認定調書を入手する必要があります。
もちろん、2級だと確信して請求を行った結果3級と判定されたような場合にでも、どのような理由で決定されたのかその経緯を知るため障害状態認定調書の開示を求めていきます。
①「現症日」
サンプルの場合は認定日請求のため、診断書は障害認定日と請求日の2枚提出となります。障害認定日及び請求日現症の日付です。
②-1「目安」
診断書の「日常生活能力判定」及び「日常生活能力の程度」を数値化し、「精神障害に係る等級判定ガイドライン」の等級の目安を使い「等級目安確認シート」を作成し、該当する障害等級が記入されます。
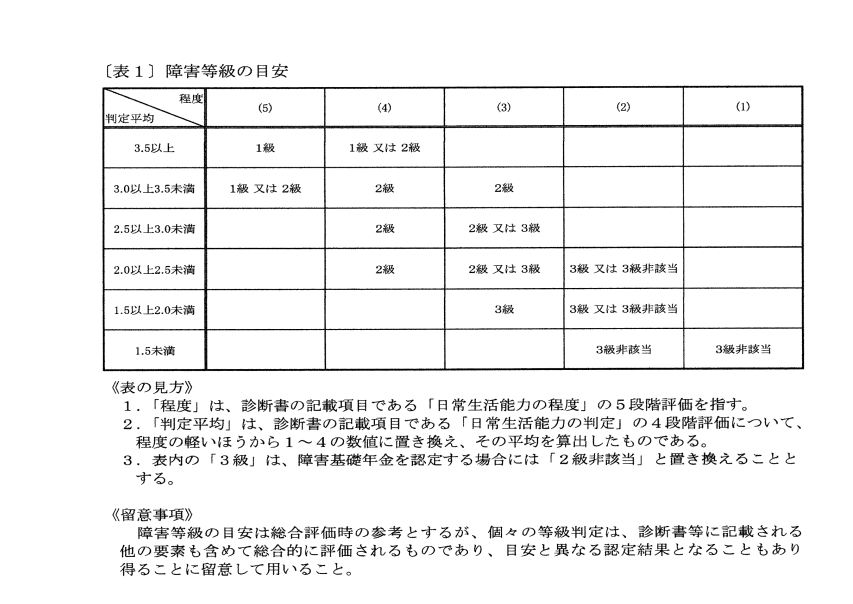
②-2 事前確認
日本年金機構の職員が「事前確認票」を作成します。等級目安確認シート右下の「日常生活能力の程度」で該当する等級を「事前確認票」の左側に記入します。さらに、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容から、「事前確認票」へ等級判定材料となる情報をピックアップし、チェックをしていきます。
抜き出した情報をもとに再度障害等級の判定を行います。目安確認シートでは2級であったものが、右欄「事前確認」では3級に○をされている場合もあります。その際には等級判定において考慮すべき要素及び根拠が記載されます(中央部分)。
*考慮すべき要素については後述
新規裁定については、請求を受けてから職員が納付要件等の確認をした上で事前確認票の作成を行い、認定医(障害認定審査医員)が当該事前確認票も参考に、医学的な観点から障害等級を判断しています。
一方、再認定では、事前確認票の作成はなく、前回の認定も参考に認定医が医学的観点から障害等級を判断しています。
| 認定医について 職員が担当する認定医は1名~3名程度であり、日程上最も早く対応が可能な認定医に依頼しているようです。 令和7年4月29日 共同通信により 障害年金判定に際し、認定医の判断を誘導するような対策文書が存在するのではないかとの報道がありましたが、職員への内部ヒアリングの結果そのような文書の存在は確認できなかったとのことです。(令和7年6月11日 調査報告書) |
|---|

③「S]
セカンド。複数(2名)の認定医により審査されたことを表しています。
④障害の等級
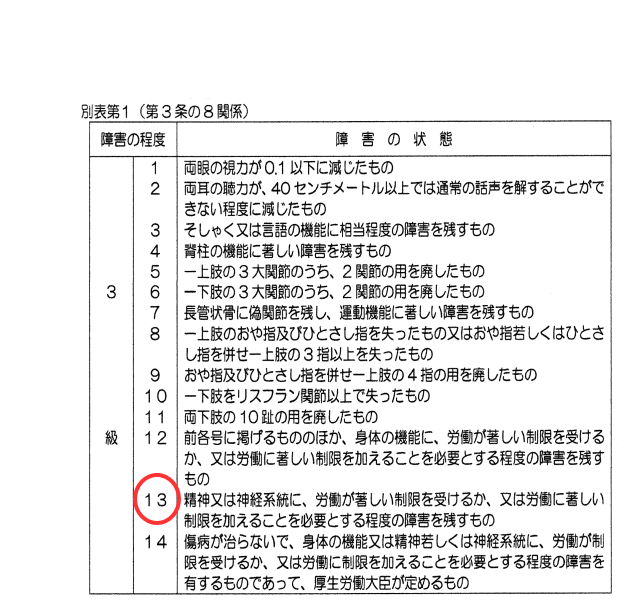
⑤適用する認定基準
障害年金認定基準第8節-2認定要領-A(08A)
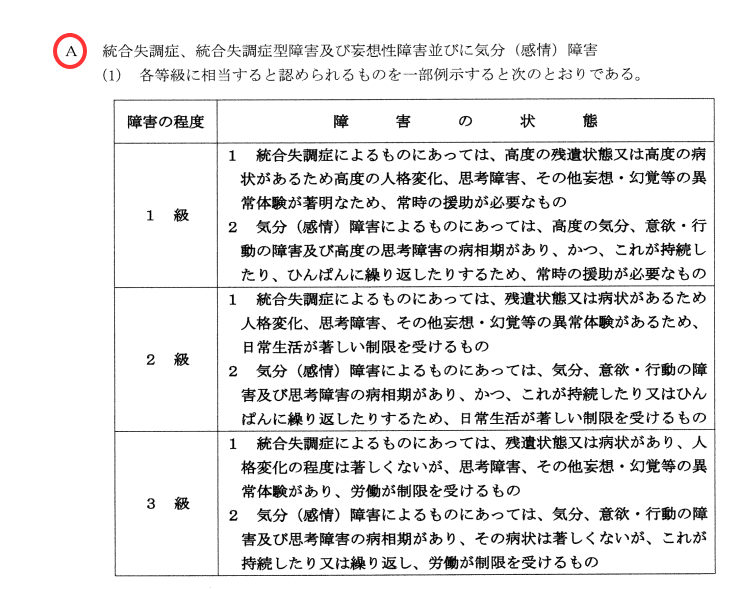
⑥特に考慮した事項の番号
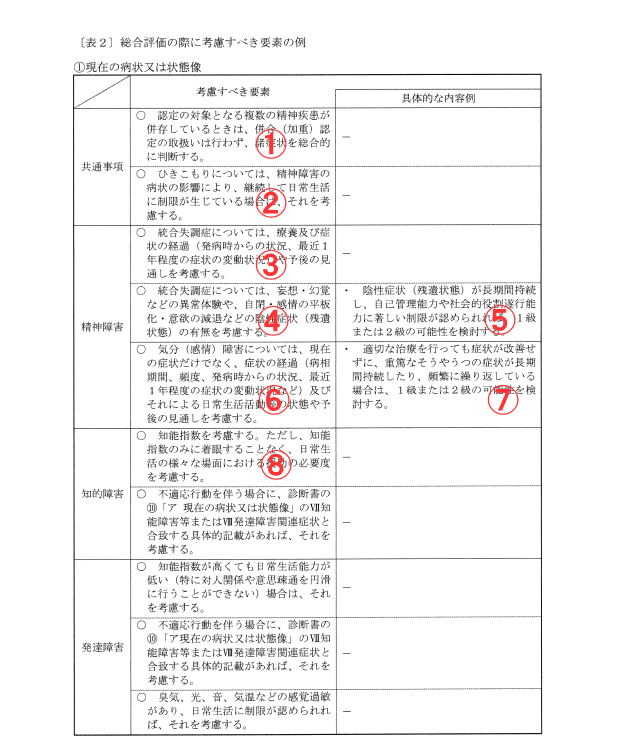
考慮すべき要素-6
「気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。
」
⑦具体的な等級判定理由、不支給・却下とした理由
不支給となった場合、2級該当を3級と判定された場合等の理由が記載されます。
例:⑩イ ⑪ カルテから○○○○あり 等
⑩、⑪は診断書(精神の障害用 様式第120号の4)の記載項目です。
*なお、具体的な等級判定理由について、「⑩ウ」や「カルテ、就労状況により3級」等の記載がよく見受けられます。
開示請求をかけて判定理由を知る上で、このような記載は判断の理由としては極めて不明確であると言えます。「⑩ウ」のどのような点が上位等級を検討する要素で、どのような点が下位等級を検討する要素なのか、明確に記載されている必要があります。
「⑩エ」を理由として、3級非該当とされる場合もありますが、一般就労していることのどの部分が下位等級を検討する要素になっているのか明確な根拠が示されるべきですが、現時点では、これまでの請求事例より推測するしかありません。

審査請求の趣旨及び理由
①趣旨
審査請求を行う上で求めていくない内容を記入します。
例:「裁定請求日において障害基礎年金2級を認定すること」
「障害認定日及び裁定請求日において障害厚生年金の受給権を認めること」
②理由
開示請求で入手した認定調書等をもとに、処分内容がどのような根拠のもとに下されたかを推測し、それに対する反論を考えていきます。
例えば、2級相当のものが不支給となった場合、
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(3)総合評価-①には「 診断書の記載内容に基づき個別の事案に即して総合的に評価した結果、目安と異なる等級になることもあり得るが、その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判定する。」と定められています。認定調書の⑦等に記載された内容をもとに、不支給と判定した理由に合理的かつ明確な根拠があるのかを考えます。
障害認定基準、精神の障害に係る等級判定ガイドラインそして過去の社会保険審査会での採決例等を元に理論構成していきます。診断書や病歴・就労状況等申立書などに記載された事実を法令、ガイドラインにあてはめ保険者の主張の矛
盾、解釈の間違い、不備を突いていきます。
残念ながら、年金事務所での相談で具体的なアドバイスをもらうことはできません。請求者一人一人で全く事情が異なってくるため一般論では対処しようがないからです。
ご相談者の中には、「診断書の内容が軽く書かれていたので、改めて主治医に診断書を修正をさせた。これを提出すれば受給できるか」とのお問い合わせをいただくことが有ります。
しかしながら、よほどのことがないかぎり診断書の修正、補正は認められないと考えた方がいいでしょう。
原処分を受け審査官の決定書の内容を知った後に、医師が請求人の要請に基づいて作成された診断書等については、当時の診療録等の客観的資料に基づいて作成された診断書とは認められません。患者に泣きつかれて修正、補正したものを後から提出しても認めないということです。

これから請求をされる皆様へ
①とりあえず自分で請求をしてダメなら不服申し立てをする。
②支援機関のサポートを受けて、年金事務所とも相談の上で手続きを進める。
③社会保険労務士に依頼する。
①②の場合
・診断書の不備を見極め、理由、根拠を示したうえで医師に修正させることがで きるか。
⇒もちろん、ごり押しでするのではなく、記載要領等をもとに記載時の留意事項 等を説明したうえで修正していただく必要があります。)
・年金事務所での説明、病歴・就労状況等申立書作成時において、情報の取捨選択をしっかりと行えるかどうか。
⇒不必要な情報まで相談、もしくは申立書に記入するとその内容が後々まで尾を引く可能性があります。
・支援機関等でサポートしてもらう際に、不支給となった場合、不服申し立て迄サポートをしてくれるか。
⇒とりあえず年金事務所で言われたとおりに書類を作成して提出をし、不支給となったら「もう無理です」では話になりません。
障害年金を専門に扱っている社会保険労務士であれば、不服申し立ても当然ながら取り扱っています(全員とはいいませんが)。審査請求等を行うことで、保険者が診断書やカルテそして申立書のどのような点を問題としてくるのかおおよそ検討がつきます。
先にも述べましたが、不備な診断書を提出すると、その後不服申立をしても決定が覆ることはありません。後出しジャンケンで請求時に提出した診断書を、審査請求の段階で別のものと差し替え、認められる等ということは非常に稀です。
要は、最初の請求が一番肝心だということです。”ダメなら不服申し立て”という発想は非常にリスクが高いです。
受給権は最初の1回目でしっかりと勝ち取る(語弊はありますが、実際、勝負所は初回請求時です)ことが重要です。
保険者がチェックをするポイントを見極め、医師への診断書作成を依頼し、障害の状態・程度及び日常生活状況等矛盾の無いように申立書を作成していく必要があります。
以上、不服申し立ては請求時の数倍労力と知識が必要となります。請求時の手順についてはネットでいくらでも情報が公開されていますが、審査請求、再審査請求についてはそのような制度があるというレベルで、実際どのようにすべきかという情報はどこを探して見つかりません。
依頼を受けた社会保険労務士は請求者の個々の状況を見極め、数日から数週間かけて審査請求書類を仕上げていきます。個々の事例を取り上げネットに情報を上げたところで、当事者以外には全く意味のない情報、知識となります(考え方は参考になりますが)。また、個人情報の絡みもあり具体的な情報入手は困難です。
*現時点で入手可能かどうかは不明ですが、
下記書籍は事例掲載が豊富で非常に役立ちます。
「障害年金 審査請求・再審査請求」(日本法令)
なお、NPO法人 障害年金支援ネットワークでは全国の社会保険労務士をご紹介しております。
審査請求をする方が良いのか、した場合の受給の可能性、さらに再請求について等、無料相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(社会保険労務士の利用を無理強いされるようなことは一切ありませんのでご安心ください)
↓↓↓大阪、奈良等一部地域を除き出張相談可能です。