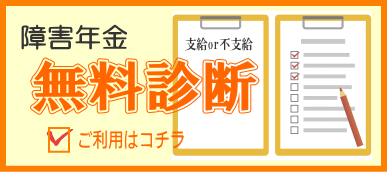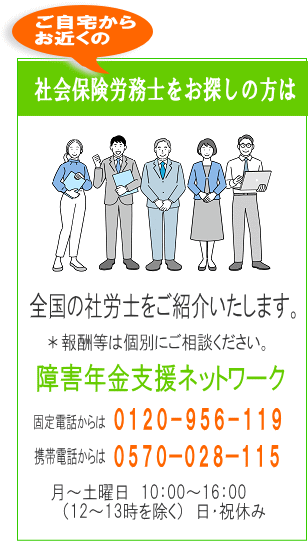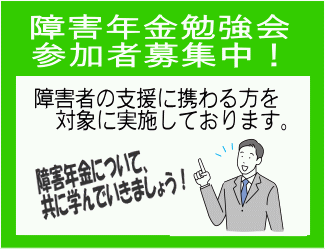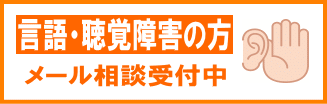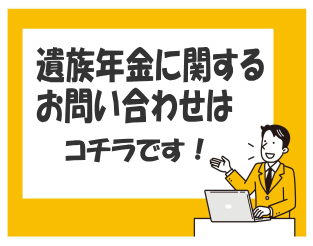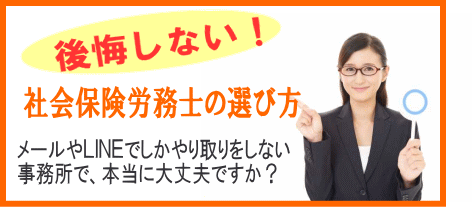神経症(F4)や人格障害(F6)は障害年金の認定の対象外とされています。
そのうち、神経症についてはF2又はF3の病態を示している場合には認定の対象にするという取り扱いとなっています。
そもそも神経症を障害年金の対象外とすることについて、明確な法令上の根拠は存在しません。神経症が原則として障害年金の対象疾患から外されている理由は、「自己治癒可能性」と「疾病利得」からです。つまり「神経症は患者自身が自らの意思で環境を変えたりして対応をとることで主体的に治癒に持ち込むことができる」、さらに「年金という長期の救済制度によりその経済的メリットを享受することで自ら治す努力を喪失させてしまう」ということです。
| 認定基準より 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。 なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。 |

| 診断書注意書き 「障害の原因となった傷病名」欄に神経症圏(F4)の傷病名を記入した場合で、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」または「気分(感情)障害」の病態を示している時は、「13 備考」欄にその旨と、示している病態のICD-10コードを記入してください。 |
傷病名がF4~F6の場合、備考欄にF2又は F3のコードが記載されていないと、裁定請求段階で支給決定となる可能性は限りなく低いです。
認定基準より、「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」とありますが、実際の所、日常生活能力の全体評価から、F4~6の程度を差し引いて認定が行われることがあります。
要は、単に備考欄にF2,F3の記入をしてもらうのみでは2級と判断される可能性が限りなく低いということです(あくまでも当事務所の実感としてですが)。
少なくともF2,F3と神経症が主にどちらの傷病が主傷病なのか、また前景に出ている傷病はどちらなのか等をはっきりと⑬備考欄に明記してもらう必要があります。
診断書①「障害の原因となった傷病名」の記載方法について
いくつかの精神疾患が併存している場合
初診日が違う場合
主たる傷病とそうでない傷病とを区別し主たる傷病から順に記載してもらう。
初診日が同時期にある場合
主たる傷病とそうでない傷病を区別する必要が無い。
なお、精神疾患には神経症とF2,F3に似たような傷病名がいくつかあります。
記入された傷病名が障害年金の支給の対象とされている傷病名かどうかよく確認しておく必要があります。
*神経症でも備考欄に「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」または「気分(感情)障害」の病態を示している旨記載することで、安易に支給につながる考えられる方がいますが、申立書も含め日常生活状況等との整合性をしっかりとあわせておかないと、結局不支給通知が送られ、不服申し立てをする羽目になります。
医師も神経症が対象にならないことを知っていますので、患者から要求されると精神病の病態を示している旨備考欄に記載をしてくれることがあります。
しかしながら、診断書⑨⑩や申立書の内容に記載された病態及び日常生活状況に整合性が無いとして不信感を持たれると、カルテの開示請求につながります。 その結果、診療録からいろいろ不都合な文言を抜き出され”非該当”と結論づけられることになります。こうなると、なかなか審査請求をしても保険者の主張を覆すことが難しくなります。
やはりポイントは、最初に提出する診断書をどのようにそつなく作成してもらうかということです。